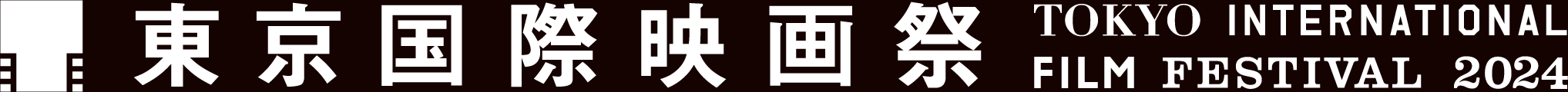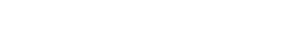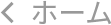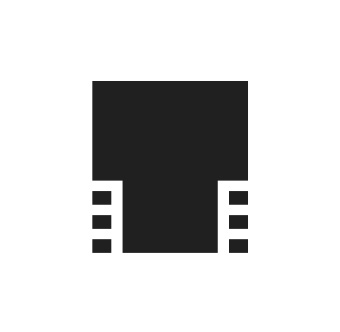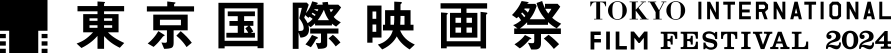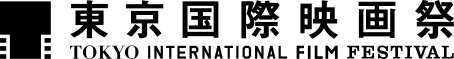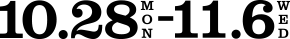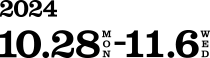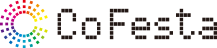10月15日(火)に丸の内にある日本外国特派員協会にて東京国際映画祭と日本外国特派員協会(FCCJ)との共催で会見を実施。ゲストとして、2009 年の自主制作による『SR サイタマノラッパー』が大きな話題を呼び、以降ジャンルの垣根を越えた形で振り幅の大きい野心作を次々と撮り続けており、今年公開の『あんのこと』も話題となった、今年のNippon Cinema Now部門の特集監督である、入江 悠監督が登壇しました。

はじめに、安藤チェアマンより「ここ2、3年の東京国際映画祭の変化というのは3つあると思います。1つ目は本拠地を六本木から日比谷・丸の内に移したということ。2つ目はプログラマーに市山氏を招いたこと。そして3つ目は国際交流に力を入れたということです。今年はますます定着してきたと思っております。この地区で行政や企業との連携が強くなり、この映画祭もようやく市民権を得てきた。市山氏のカラーも定着していて、アジアの映画祭としての特色が鮮明になってきた。そして、交流ラウンジという場所を通じる交流が量的にも質的にも向上してきた。それに加え、今年は特に映画人材の育成と女性の活躍ということに焦点を当て、力を入れていきたい」と語りました。
次に、市山プログラミング・ディレクターより、ここ1年の日本映画を対象に特に海外に紹介されるべき日本映画という観点から選考された作品を上映するNippon Cinema Now部門において、今年特集される入江悠作品が紹介されました。
市山氏は、「これまでもコンペティション部門、ガラセクション部門などで実績のある監督を取り上げいるが、Nippon Cinema Now部門ではこれからの日本映画を担う人材の作品を取り上げている。福永壮志監督や小田香監督の新作だけでなく、以前Amazon Prime Video テイクワン賞を受賞し、同社によるにファイナンスを受けた金允洙(キム・ユンス)監督の『あるいは、ユートピア』という作品が上映となる。これは、東京国際映画祭が人材育成に力を入れていることを象徴している。そして、『雲ゆくままに』のヤン・リーピン監督も昨年テイクワン賞を受賞し、現在Amazonと組んで新作を撮ろうとしている。今回の特集をする入江悠監督は、大きな商業作品やインディペント作品の両方を行き来しながら撮っている監督で、今日上映する『あんのこと』が素晴らしく、今回監督の足跡を振り返る企画として特集することを決めた。是非入江監督の作品をこの映画祭で改めて発掘してほしい」と語りました。
最後に、入江悠監督が東京国際映画祭にて特集されることについて聞かれ、「日本には素晴らしい監督が沢山いらっしゃって、作家性のある方が同世代にも沢山いるなかで、なんで自分が選ばれたのだろうと困惑したのが正直なところです。ただ、人生で何度もあることではないし、『あんのこと』が自分のフィルモグラフィーの中で特別な一作になるだろうと感じていたので、そのタイミングで呼んでいただけて、嬉しく思っています。この特集をしていただくことで、今後自分がどのように映画と向き合っていくかを改めて考えるきっかけに出来れば」と特集上映にあたっての想いを明かしました。
その後、登壇者3名に対して、来場者からの質疑応答が行われました。
【質疑応答】
Q.先週釜山映画祭が開催されましたが、そこでも話題となったストリーミング作品の台頭に関して、東京国際映画祭においても何か影響などを感じるか
市山プログラミング・ディレクター:オープニングをはじめ釜山映画祭では、配信映画がかなり目立っていた。韓国では若い人たちが配信作品を沢山みる様になって映画の興行収入が減ってきているという。日本の場合は、依然として映画館に行く観客も多いので、ストリーミングが現段階では映画産業に大きな影響を与えてはいないのではないかと思う。東京国際映画祭のセレクションに関しては、日本映画はかなりバリエーションのある作品を揃えられたので、ここに関してもバランス的に大きな問題は起きていないと感じている。ただ、数年前よりTIFFシリーズにおいて配信映画を取り上げるセクションを設けてもいるが、それは配信作品においても素晴らしいものも多く、そういった作品は取り上げるべきだと考えているからだ。
Q.入江監督はテレビシリーズは過去に扱っているが、配信に関しても興味はあるか
入江監督:実は今年の夏に配信作品を手掛けた。スタッフなど作り手側としては、映画もドラマもストリーミングも変わりなくなってきている。僕らは、映画とは何なのかということをもう一度定義しなければならない時代に来ている気がする。
Q.配信作品を手掛けることで、制作者にとってはこの仕事を続けていく機会になっていると思うか
入江監督:はい、そう感じます。ただ、制作者や俳優を取り巻く環境はそこまで改善されているとは思わないです。
Q.釜山映画祭において、Netflixはもはや映画祭をある種マーケティングのプラットフォームにしたと思う。東京国際映画祭はどうか
市山プログラミング・ディレクター:作品次第だと思う。もしオープニングやクロージングにふさわしい配信作品が出てきたら、その時には改めてきちんと考える必要があると思う。
Q.今年上映される日本映画について教えてください
市山プログラミング・ディレクター:コンペティション作品で取り上げる3作品について話したい。片山慎三監督の『雨の中の慾情』は、原作の漫画の雰囲気を出すためにすべて台湾で撮影されたもの。吉田大八監督の『敵』は全編モノクロ映画で、シュールレアリズム的な設定を使った面白い作品。そして、大九明子監督の『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、彼女のベストの作品だと思う。特に俳優の演技が素晴らしく、長回しのシーンは必見です。
Q.海外に向けて訴えたいものはあるか?
安藤チェアマン:吉田大八監督の『敵』に関して、主演の長塚京三さんとは同じ演劇を目指した仲。老境を描いた作品で、大変身につまされる。このように沢山の魅力に溢れた興味深い作品が数多く上映されるので、是非多くの方に映画祭に足を運んでいただきたい。
また『あんのこと』上映後に、入江監督への質疑応答が行われました。
<上映後>
【入江悠監督 マスコミからの質疑応答】
Q. 本作は実際に起こった事件が基になっていると伺いましたが、どのように事件を知り、映画化となったのでしょうか?
入江監督:プロデューサーから、薬物依存症を断ち切って夜間学校で学んでいた女性が、コロナ禍で命を絶ってしまったという新聞記事を見せてもらったのと、刑事が被害者救済活動を私物化して捕まった別の事件の週刊誌の記事を見せてもらい、それを元に脚本に起こしてみないかという話をいただいたのがきっかけです。コロナ禍を経て、なぜ彼女が自死という道を選んでしまったのか、東京ですれ違っていたかもしれない彼女に関して、なぜ自分は気づくことが出来なかったのかという思いから映画化してみたいと思いました。
Q. 主演の河合優実さんについて教えてください。
入江監督:彼女は19歳くらいの頃から知っていて、その頃から演技に対する意気込みが凄かったんです。プロデューサーから彼女を勧められたのですが、彼女と一緒にモデルになった主人公の輪郭を求めて、依存症の方に話を聞きに行くなど、一緒に作品を作ったという感じです。
Q. 週刊誌の記事によってモデルになった人は自殺されたと考えていますでしょうか?記者の責任はどうとらえますか?
入江監督:個人的には記者の方に責任はないと思っています。ただ、これは実際の記者もそうですが、刑事が更生グループを私物化していた側面に気づかなかった所に衝撃を受けたという風に思っています。
Q. 監督が脚本を書いている際に、この結末を考えていたのでしょうか?
入江監督:この映画の上映後のQ&Aでも、彼女が最後救われるという結末にする選択肢はなかったのかと度々質問があったのですが、この映画を作る出だしが、彼女が自殺されたという記事からスタートしていて、なぜ彼女がそういった選択をされたのかを知りたかったというのがあります。主演の河合優実さんも、モデルになった方を同情の対象にしたくない、撮影中に彼女と手をつないでいる様な気がするとおっしゃっていて、彼女の人生を追体験していたと思います。河合さんを通して僕たちは彼女の気持ちを知ることが出来たのではないかなと考えています。
Q. 同じシェルターに住んでいた方から、子供を預かるというシーンがあると思うのですが、それも実際にあった事件なのでしょうか?
入江監督:あそこのシーンはフィクションなんです。虐待は世代を超えて連鎖するという研究があるのですが、あんはその連鎖を断ち切るということが出来るのではないかという希望を入れたかったのです。
Q. ヤングケアラーなど、世界中でも問題になっていますが、本作は海外での上映も念頭に撮られたのでしょうか?
入江監督:外国のオーディエンスを考えていたわけでないのですが、カメラマンの方がシンガポール在住の方で、その方と撮影中に日本固有の問題なのか、普遍的な問題なのかなども話し合ったりしていましたので、意識した部分もあったのかもしれないです。
Q. 撮影中にご自身が感じられていたこと、観客に感じでほしいことはどういったことなのでしょうか?
入江監督:自分が彼女に近づきたかったというのがあるので、観客にどう感じてほしいという意識はあまりありませんでした。社会の閉塞感が漂ってきて、圧迫されるのが怖くて、かなり撮影当時は苦しかったというのが率直な気持ちです。東日本大震災、コロナ禍と大体10年毎に社会が息苦しくなるようなことが起こってきていると思います。これからも同じようなことは起こると思うし、また10年後にそんなことが起こった時に、10年後のあんみたいな人が一人でも少なくなってくれたらいいなと完成時には思いましたね。