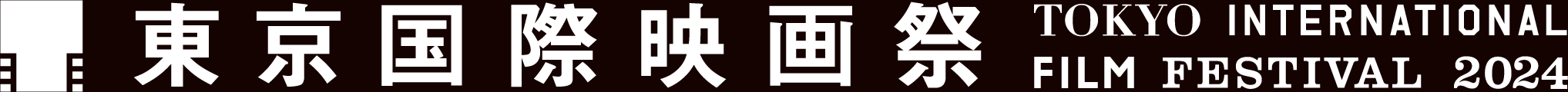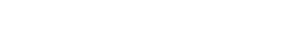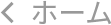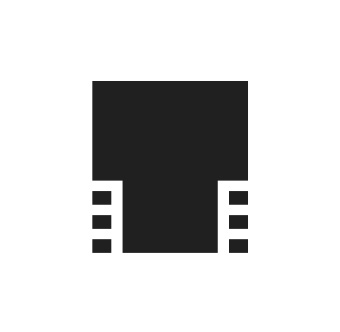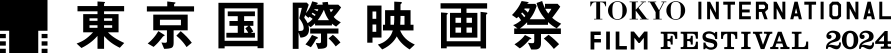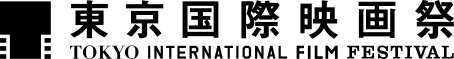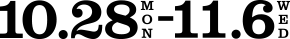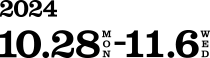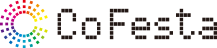第37回東京国際映画祭コンペティション部門出品作
『敵』
吉田大八監督公式インタビュー
主人公は、妻に先立たれ、すでに大学教授を辞して10年が経つ老齢の男性。父の代から続く日本家屋で平穏に過ごしているが、ある日、パソコンの画面に「敵がやってくる」という不穏なメッセージが流れる…。
吉田大八監督の『桐島、部長やめるってよ』(13)は、観客による口コミで、6か月以上のロングランを達成し、日本アカデミー賞や、様々な主要映画賞を総なめにした。もちろんその後も、大八印は順調に刻印され続け、私たちを楽しませてくれている。
西原理恵子や、山上たつひこといった曲者たちの漫画原作を映画化し、また、角田光代や三島由紀夫といった卓越した作家の原作も映画化してきた。
今回の『敵』の原作者は筒井康隆。これまた部外者から言わせてもらえば、難易度が高いのではないかと思う。しかし、長年の筒井ファンだからと、監督は製作の困難さに関してさらりと語る。
挑戦とか冒険とかではなく、映画に軽やかに向かうその才覚が、この映画にも生きている。

──『紙の月』(2014)以来、コンペティション部門に選ばれるということに関してのお気持を聞かせて下さい。
吉田大八監督(以下、吉田監督):評価してもらって注目を集められるのは、これから劇場公開を控えている映画の第一歩として、本当に有り難いです。
──『敵』のオフィシャルサイトでは筒井康隆さんが「映像不可能」と仰っていて、今回はかなりの挑戦だったと思うのですが、如何でしょうか。
吉田監督:まあ、どんな原作であろうと、映像化は大変に決まっているので。
昔から、好きでさえあれば道は見つかるはずという確信はずっとありますね。あれこれ考え続けること自体が喜びですから。
映像化不可能だったものを映像化できているかどうかは、 僕にはジャッジできませんが、筒井先生からそういうお言葉を頂けたのはすごく嬉しかったです。

──今回、モノクロが素晴らしかったと感じたのですが、「敵」を映画化しようとする時からモノクロであると決めていたのですか。
吉田監督:最初は考えていませんでした。ただ、舞台となる家のイメージはありました。
できるだけ古い日本家屋、でも純和風ではなく多少、和洋折衷にもなっている、そういう家を舞台にした映画を参考のために結構、観たのですね。昔の映画が多いからモノクロが必然的に多くなって、それでいつの間にか影響を受けたのだと思います。
それと、主人公のストイックな生活を描くにあたって、やはり抑制的なモノクロがふさわしいだろうなという直感みたいなものもありました。
──主人公は、朝起きて、ご飯を炊き魚を焼いて、コーヒー豆も挽く。とにかく色々と細かい所作がすごくよく映し出されていると感心しました。これらの食事シーンは原作通りなのでしょうか。
吉田監督:原作では、映画以上に細かな描写が前半、延々と続くのですが、それがすごく好きで。もちろん全部は無理ですけれど、そのエッセンスをできるだけ忠実に再現したいとは思いました。
──基本、撮影は家の中ですよね。それなのに世界が大きく感じました。
吉田監督:この映画に限らず、限定された空間の中で世界の広がりをどう感じさせるかということは、いつも考えていますね。
家、学校、職場など、ある限定した空間の圧力をできるだけ高めて、バンとはじけた時の飛距離を稼ごうという志向、というか癖があるのでしょう。

──主人公のPCに、敵が攻めてきたと表示されるあたりから、この元教授の生活が、現実か否かという感じに変わっていくようにも思えました。監督は、その主人公の有り方の境目における敵を、どう意識したのでしょうか。
吉田監督:最初はもちろん、死とか老いのメタファーとして捉えましたが、結局は人間が生きるにあたって何かそういうもの、敵の存在を逆に必要としてしまうのじゃないか、というようなことを考えました。だから乗り越えるべき壁と言い換えてもいいし、生きる目的と言い換えてもいいし。
映画を作るプロセスの中でも考えが変わっていったのですが、初めて原作を読んだ若い頃は、最後まで姿が見えない敵に追い詰められていく不条理として、楽しんだ部分が大きかったんです。でも、 自分もそれなりに歳を重ね、主人公にとっての敵の意味がより切実でリアルに感じられるようになりました。
さらに、撮影のあいだ、長塚さんが主人公として敵に向き合う姿を見つめ続けるうち、敵のイメージ自体がどんどんバージョンアップされていった気がします。
──原作では、主人公が「夢か現か」というか、いわゆる老人の呆けというニュアンスもあるようですが、確かに、映画の中の主人公はきちっと生きている感じがします。
吉田監督:原作を何度か読み返すうちに、それまで普通にできていたことができなくなる老人性の症状というよりは、人生の最後のステージで、もう一度会いたい人とか、もう一度経験したいことを半ば無意識に求めて、そのために夢や妄想の世界へ積極的に身を投じずにはいられない主人公像が浮かび上がり、それを描きたいと思いました。
──どことは言いませんが、双眼鏡の使い方とか小道具に驚かされるところも。
吉田監督:双眼鏡自体は、原作、前半で物置にしまいこまれた古道具のひとつとして紹介されるのですが、そこからかなり発展させました。やはりレンズを通して人や物を見る、という点で映画的な奇跡を託しやすい小道具なのかもしれません。

──『敵』のオフィシャルサイトで、監督がこういう映画は2度と作れない、というようなコメントを出していて、それは今回のようなアートフィルムではなく、この先はエンタテインメントよりを作らなくてはならないとか、そういうことを考えておっしゃったのでしょうか。
吉田監督:これまで、自分のつくってきた映画をアートフィルムかエンタテインメントかとは意識しなかった、というか、そんなの両方ともに決まってるだろと思ってきました。それは『敵』も同様です。
ただ今回は、監督である自分の「作りたい」という気持ちを、他の様々な企画成立に絡む事情より、常に優先してもらえた有り難さをひしひしと感じています。もちろん予算やスケジュールにおいて、その規模に伴う制限というのも当然あるのですが、それを含めても、こんなに自由に映画を作れたのは、映画というメディアの置かれた状況を考えると、本当に幸運なことだったと思います。
2024年9月25日 東京ミッドタウン日比谷 取材構成 小出幸子
第37回東京国際映画祭 コンペティション部門
『敵』

監督/脚本:吉田大八
原作:筒井康隆
キャスト:長塚京三、瀧内公美、黒沢あすか、河合優実、松尾 諭、松尾貴史