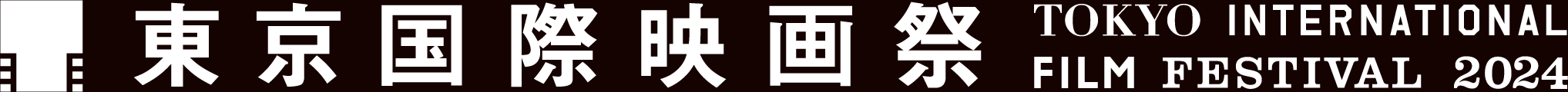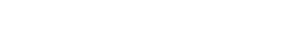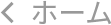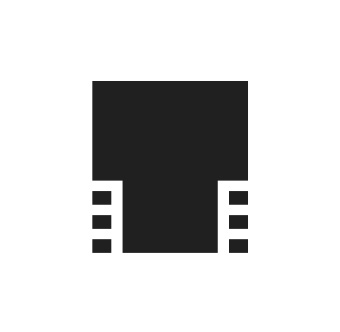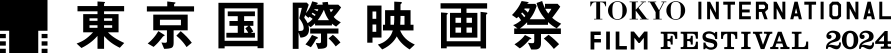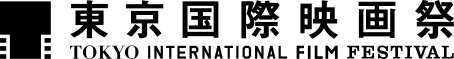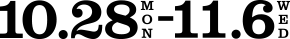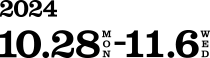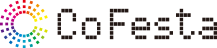東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月3日
アジアの未来
『昼のアポロン 夜のアテネ』
エミネ・ユルドゥルム(監督・中央)、エズキ・チェリキ(ダフネ役・右)、バルシュ・ギョネネン(ヒュセイン役・左)

孤児として育ったダフネは、かつて自分を捨てた母親を探して、ギリシア様式の遺跡が数多く残る海辺の古都シデを訪れる。そこで彼女が出会うのは、かつてそこで暮らしていた人々。娼婦、巫女、革命家など、さまざまなキャラクターとの出会いによって、彼女は母親の手がかりをつかみ、再会へと導かれていく。
2018年の『シレンズ・コール』でプロデューサーを務めたエミネ・ユルドゥルムによる初監督作品は、オーソドックスな自分探し・家族探しの旅を、現代社会の問題やファンタジーを交錯させながら描いた意欲作だ。本作の製作裏側を、監督、そして主軸となるキャラクター・ダフネとヒュセインを演じたエズキ・チェリキと、バルシュ・ギョネネンに聞いた。
──長編監督デビューおめでとうございます。まず監督にうかがいます。アイディアの着想は何だったのか、またこの作品をデビュー作に選ばれた理由を教えてください。
エミネ・ユルドゥルム(以下、ユルドゥルム監督):このテーマを選んだ理由は、今の世相に由来しています。世界は非常に難しい時期にきていて、人間らしさや人々が歩んできた歴史とのつながりをないがしろにしがちになっていますよね。だからこそ、それらはすごく大事になっていると思うんです。
これまで人間は、何千年も同じように文化・社会を育んできたのに、それを忘れてストーリー性を失っているんじゃないか。人々のコネクションや情熱、人間らしくあるべきということを描きたくて本作をデビュー作に選びました。

──脚本の推敲に掛かったのはどれくらいでした? また、役者のおふたりには、キャスティングがどのようにに行われ、脚本を最初に読んだ時の感想を伺いたいです。
ユルドゥルム監督:トータルで2年間くらい推敲していました。もちろん2年間毎日やっていたわけではないですけどね(笑)。
はじめにロケハンから始めています。4日間くらい、本作の舞台にしているシデに実際に行ってみました。古代から続いている街ではあるんですが、トルコらしいというよりは、どこか宇宙的なものを感じ、すぐに気に入りました。しかも、古くから続く街だからこそ、そこで暮らしを営んできたかつての人々…いわゆる幽霊がいっぱいいると思ったので、その幽霊の話にしようと考えたんです。そこで思い浮かんだのが、エズキ(・チェリキ)さんでした。
2018年に行われた第31回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品した、私のプロデュース作品『シレンズ・コール』でもエズキさんとご一緒して来日もしていますが、そのご縁を思い出したんですね。そこで、本作の主人公は女性にし、エズキさんをキャスティングすることを想定して脚本を書き始めました。
バルシュ・ギョネネン(以下、ギョネネン):私は監督が手掛けた前作(『シレンズ・コール』)を見たことが、監督とご一緒したいと思ったきっかけです。それで本作の脚本を読ませていただいたんですが、一気にほれ込みました。ストーリーもすごかったし、私が演じたヒュセインという役はすごく面白く重要なキャラクターです。役者としては難しいことでしたが、エズキさん演じるダフネの“光のサイド”を演じることができたらと思いながら挑みました。

エズキ・チェリキ(以下、チェリキ):監督とは前も一緒にお仕事したご縁もあり、このプロジェクトに参加できてすごくうれしかったです。脚本が完成する前のドラフトから拝読していたんですが、ストーリーも私が演じたダフネもすごく魅力的でした。ダフネはすごく複雑な人間性をもっているキャラクターなので、いいチャレンジをさせていただいたと思っています。

──キャスティングはオーディションではなかったんですね?
ユルドゥルム監督:オーディションではなく、プロデューサーと私でかなり時間をかけて適役を探しました。舞台を見に行ったり、エズキさんからこの人に会ってみたらどう?とご提案いただいたりして、多くの俳優を吟味しています。映画の画的に合う人を揃えたかったのでかなり時間をかけました。
──脚本を書く際にロケハンから始めたとおっしゃいましたが、ロケハンで得られた具体的なこと、インスピレーションが湧いた瞬間があったら教えてください。また、役者の方々には、それほどまでに監督がこだわったロケーションが持つ力が芝居にどの程度影響があったのか教えてください。
ユルドゥルム監督:日本でもお寺や神社にいって、そこで触って見たりして歴史とのつながりを感じたりしますよね? そういうふうに、トルコでも遺跡に行ってみて、その場にいるかつての人々がまだいることを感じとることができるものなんですよ。トルコには戦争も含めて悲しい歴史がありますが、そのときにきちんと終われていないストーリーがたくさんあって、その一部でも拾えたらいいなと思いました。
ギョネネン:夏場はかなり観光客が多い街なんですが、私たちが行ったのは12月で観光客はほとんどいませんでした。イスタンブールでリハーサルを何度もしたあとで、実際にこの場所に行ってみたら、ロケーションの力をすごく感じましたね。力強いし、作品の中に入ったかのようなちょっと変な感じもしました。
ロケーションの影響は多分に受けましたし、撮影していくなかで物語の中にいるキャラクターと同じように、家族みたいな一体感が生まれたなと感じました。
チェリキ:私はこの作品に関わるまでシデには行ったことがなかったんです。そのため、キャストやスタッフがシデに集まる1週間前にひとりで滞在し、いろいろ見ることにしました。
デフネを演じるためには、複雑な感情を背負わなければならず、少々不安があったんです。でも、このロケーションだからこそエネルギーをもらえたし、キャラクターを作る上でもすごく役立ちました。ロケーションの持つ力がいい方に作用したと思います。
──どの役もすごく多面的ないろんな顔を持つキャラクターとして描かれています。この複雑性を監督の頭の中でどう整理をつけていたんでしょう。また、おふたりは役作りでの具体的なリサーチはどのようにされましたか?
ユルドゥルム監督:撮影中に何度も、「6人も大事で複雑なキャラクターがいる。私、何やってんだろう」って思ったりもしました(笑)。でも、映画を撮ることは、いわばコラボレーション。美術や音楽やプロデューサーなど、セットにいる人全員が、それぞれが自分のベストを尽くしているので、彼らを信頼するよりほかありません。
特に彼らふたりの俳優は、誰よりも自分の演じる役のことをわかってくれているので、私よりも役のことを理解しているという信頼感がありました。たとえば、彼が演じたヒュセインは、撮影中に脚本を変えたところもありましたが、それも彼がうまく自分に取り込んでくれたんです。私ひとりでは、この作品の舵取りはできなかったと思います。
ギョネネン:(イスタンブールでの)リハーサルである程度の役作りをした感じです。
ユルドゥルム監督:そうそう、ほとんどがリハーサルで作り上げたものでしたね。
ギョネネン:私の場合、ヒュセインが方言を話す役だったこともあり、言葉遣いを学ぶのも必要だとわかりました。そこで、ディヤルバクルという、シリアに近いトルコの南東部に実際に行って方言の習得をしています。
チェリキ:私は、最初に声をかけていただいてから5年という歳月の中で、監督とはいろいろ話していたので、そこで徐々に作っていった感じでした。たとえば、母と娘の関係、または親に捨てられるってどういうことなんだろう、とか、聖母のようなものは存在するんだろうか、とか。ダフネのイメージについて、いろいろ話したのが役作りの助けになったと思います。
ユルドゥルム監督:そこに加えるとするなら、カメラのフレームの中できれいに見せるためにどうすべきか、ということも俳優たちと相談をしましたね。
──大筋としてはシンプルな物語ですが、リアルのパートとファンタジーのパートがありますし、キャラクターも複雑で単純な芝居で終われない作品ですよね。監督としての舵取りをするにはなかなかの苦労があったと思います。
ユルドゥルム監督:業界で20年以上働いてきたこともあり、初監督とはいえ慣れた仕事の現場でした。もし私が25歳で初監督だったら…厳しかったでしょう。私は政治的活動家ではありませんが、世界または自国の政治のあり方についてよく考えています。私がよく考えるテーマだったことも、意欲的に仕事できた原動力になっています。
また、映画は人と時間とお金がかかること。小説を書いたり絵を描いたりといった、ひとりで完結することではありません。自分が映画を監督するなら、やる価値がないと!…と思ったら、重いテーマになっちゃいました(笑)。
──おっしゃる通り、このテーマ性でいい俳優とスタッフを集められたのはラッキーだったかと。それゆえに、資金集めが一番難しかったのではないでしょうか?
ユルドゥルム監督:そこに関しては運がよかったんですよ。キャスティングはもちろんですが、資金面では苦心したんです。文化庁のスポンサーシップを申し込んだところ許可が降りず、2回目の申請でなんとか通ったものの、低バジェットのプロダクションになることは決まっていました。
すごくラッキーだったのは、ロケ地のシデでは大きな援助を受けることができたんです。シデの5つ星ホテルがスポンサーになってくれて、撮影の1か月間、40人のクルーを無料で泊まらせてくれたんです。ホテルのオーナーさんが、ぜひシデを映画の舞台として描いてほしいと思ってくださったこともあって、それが実現しました。ロケの滞在費はバカにならないですから本当に助かりました。いい目的をもって自分を信じていれば、応えてくれる人は自ずと見つかる、というのがトルコのことわざであるんですが、まさにそれを体験した気分です。
──それはかなりの経費圧縮になりましたね。最後におふたりにうかがいます。このチャレンジによって得られたことを振り返るとなんだったと思いますか?
ギョネネン:ヒュセインは人生の楽しさを体現するキャラクターでした。また、積極的かつ自発的に行動を起こすキャラクターでもあります。じつはトルコ映画全体に言えることなんですが、この10年くらい、こういうキャラクターはほとんど出てこず、別のジャンルで同じようなタイプの作品、キャラクターが多かったんですよ。それらとは違う、深みのあるキャラクターを演じられたのは、役者としてエキサイティングなことだったと思います。
チェリキ:その通りですね。トルコ映画は、女性が主人公という作品がほとんどありませんし、あったとしても過剰にフェミニンな役だったり、セクシャルなシーンを求められる役だったり…。売春婦かお母さんか、それくらいしか選択肢がなかったんです。この作品は女性を主軸に描いたストーリーですので、すごく勇敢な作品だと思いますし、そこで主演させていただいたことは私のキャリアにおいて重要なものになっていると思います。

インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)