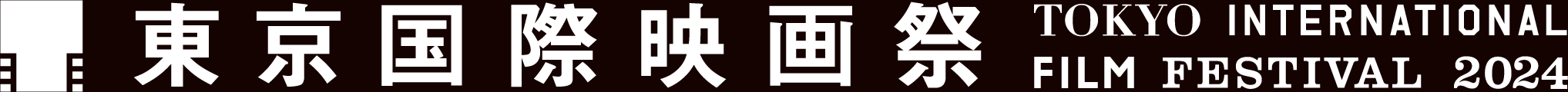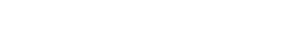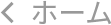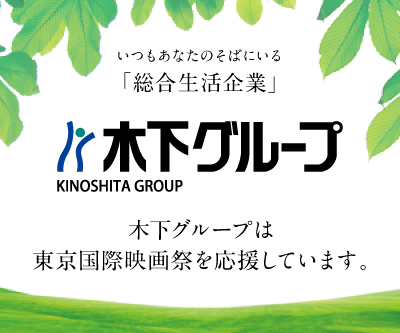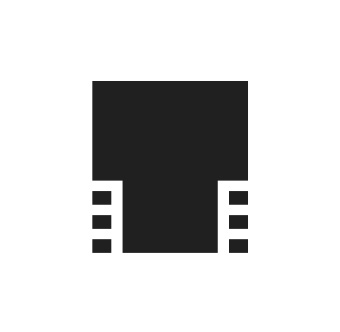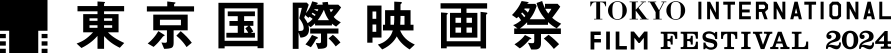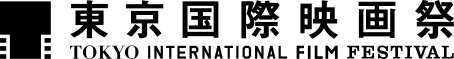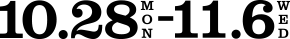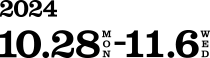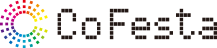11/1(金)ワールド・フォーカス『ペペ』上映後、ネルソン・カルロ・デ・ロス・サントス・アリアス監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
ネルソン・カルロ・デ・ロス・サントス・アリアス監督(以下、監督):皆さん、本当に早い時間からお越しいただきましてありがとうございます。本当に感動しております。日本に来ているのが夢のようです。
アルベルト・カレロ・ルゴさん(ラテンビート映画祭プログラマー/プログラミングディレクター):皆様、アルベルト・カレロ・ルゴと申します。ラテンビート映画祭の担当ディレクターをさせていただいてます。ラテンビート映画祭は、今年で21回目になりますが、今回の映画祭では、動物が主人公の作品が2作品ございます。非常にオリジナリティに富んだ素晴らしい作品だと思います。
皆様のQAでもちろん質問をお受けしますが、その前に1問だけ、私からネルソン・カルロ監督に質問させていただきます。
ネルソン監督はドミニカ共和国出身で、この映画をコロンビアで撮影しています。このアイデアはどこから生まれたのでしょうか。そして、動物たちが監督に協力をしていて、まるで俳優のような演技をしていますが、どうしてそのようなことが可能だったのでしょうか。
監督:”Cocote”(2017年の作品)という作品を撮り終えて、コロンビアで旅をしながら友人を訪ねていました。カミロという友達がいるのですが、彼はアーティストであり、彫刻家でもあります。彼の家に泊まっていた時に、カバの大きな彫刻のようなものがあり、それに対して”G.I.ジョー”のような小さな兵士たちがいて。あの兵士たちは、アメリカナイズされていることの象徴なのですが、その友人に「これ何?」と聞いたところ、彼が、2009年にこのペペが殺処分されたという「アメリカで殺された唯一のカバ」の話をしてくれました。アメリカ大陸にカバがいるだなんて私は知らなかったのですごく驚きましたが、彼の話してくれた話が実は少し間違っていたんです。
彼が話したストーリーでは、こうでした。(カバは通常、一夫多妻制と言われていて)この映画にも出てきた、雄の中で一番強いボスだけがその川に残り、他の雌と性交したい時にはこのボスと戦って勝たなくてはいけません。負けてしまうと、その川から1頭だけで出ていかなくてはいけない。
映画の舞台となるこのコロンビアのマグダレナ川には非常に重要な意味があり、スペイン兵がこの川から内陸部まで入りこんでいったことで、コロンビアの植民地化が始まりました。そして、この川にコロンビアの軍隊が来て、カバを殺処分したのです。ただ、殺処分は、はじめは失敗に終わります。その次には、1960年代から住んでいたドイツのハンターを連れて来て殺処分を試みました。ドイツの白人エリートの中では狩りをするのが習慣になっているのですが、彼もそうで、ナミビアで狩猟をしていた方でした。こうして殺処分を逃れながらだんだんペペは川を下って行きますが、自分がどこにいるか分からなくなり…ということになります。
これに関して、植民地化の後の動きを色々と調べたところ、こうして群れから離れていったこのカバは、実際には、1頭だけではなくて、必ず雌と一緒にその土地を離れ、違う土地で家族を増やしていったということがわかり、この点を私は非常に面白いと思いました。
──Q:このような主人公が動物という作品は色々とあると思いますが、非常に有名なのは1966年のロベール・ブレッソンのロバを主人公にした『バルタザールどこへ行く』だと思います。この映画から影響を受けましたか?
監督:(即座に)NO!ブレッソンに関しては影響を受けていません。ヌーヴェル・バーグはもう十分だと思います。
(会場笑い)
──Q:ドイツ人たちが観光客の役などで出てきますが、これは哲学的に見せる意図があるのでしょうか。
監督:ドイツ人と仰っていた方は、実はアフリカンなんです。
私は、今までずっと仕事をしてきて、言葉を非常に大切にしてきました。筆記でなくて、口述で話すことを、です。私はカリブ出身ですが、歴史というものを口述で伝承するということがこの先だんだん増えてくると思います。私たち西洋人も、そうでない人も、歴史の中で植民された側とした側どちらの立場もあります。口述で伝承していくということは、地域に根付いたものであり、そしてその地域を作ることに繋がっていくと思っています。
『ペペ』の中でも、歴史を形成してきたものには、4つの言語が関わっているとしています。そのことがとても大事だと思うのです。
まず、私の哲学、そして美意識がこうした言語に関わっており、一番最初にペペが話すのは、劇中にも出てきた、南西アフリカのナミビアで使われているムブクシュ語です。
次に、アフリカンというのは、支配された、植民地化された南アフリカの白人のアフリカンです。そこからアパルトヘイトが生まれたわけですが、ナミビアというのが南西アフリカにあたります。ナミビアはドイツの植民地になりましたが、実は20世紀の一番最初のジェノサイドはドイツ軍によって行われた、ナミビアのヘレロ・マナ族に対してのものでした。第1次世界大戦でドイツは敗戦します。そして、この植民地はイギリス(かつてイギリスの自治領だった南アフリカ連邦)のものになりました。第2次世界大戦では、イギリスはこの土地の統治を少しずつ部族に任せるようになりました。と言っても、その地域の人たちに返したわけではなく、南アフリカの白人に渡したのです。これは最悪の状況でした。
そして、スペイン語もコロンビアでは使われています。ペペが話す言葉は、カリブのなまりがあるので、ドイツ語ではないんです。ペペは本来だったらドイツ語を話すべきなのかもしれませんね。映画の中でペペのセリフに、「私たちに可能性をもたらしてくれるものもある、しかし私たちの可能性を全て奪ってしまうものがある。」というセリフがあります。ペペという存在が、寓話的に伝わっているのは、ドイツの植民地としてその歴史をはじめ、何十年も何百年も経ったのち、またドイツのハンターに殺される。植民地としての歴史が巡り巡っていると思いますし、この映画は、そうした話になっています。
──Q:ペペの視線と、それから人間の視線とを描かれている部分の書き分けには、対比の意図があったように推測しましたが、その点をお話しいただきたいです。また、カンデラリオという男性のキャラクターは、どのように考えられたのか教えてください。
監督:まず、最初に言うべきだったんですが、、こうして、私を日本に招いていただく過程では、とても大変な作業があったんです。なので、まず最初に、今回の件で色々と協力してくださった大使館の方々、アルベルトさん、そして映画祭の事務局の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。本当に感謝しております。まず、それを言わせてください。
そして、質問にお答えすると、今カンデラリオの話題が出ましたが、私は色々な歴史の本やコロンビアなど、地域の書物を読みまくりました。私の目的ははっきりしていたんですが、やはり、現地に行くとその土地の人々に会い、文化とか習慣にも出会うと色々な影響を受けました。男らしい社会というか、男性性を誇示する社会で、どちらが大きいのかというようなことを、男同士で言い合うような部分が未だに残っているんです。やはり、世界中を見ても、未だに権力を握つ人間は男性の方が多い。そうした意味で、私のこの映画のテーマの一つは、男らしさを研究するということでもありました。
そして、私は映画学校に行くことがあるんですが、この作品の話をしたときに、(劇中では、ペペの視点と人間の視点を描き分けているが)視点は変えないべきだという意見も貰ったんです。ただ、それに対しては、色々な挑戦をしていいんじゃないかと私は思いました。実験的な映画も色々と研究したうえで、4年かけて撮っているんです。その間、ジャングルで1人で暮らしていて、本当にたくさん考え事をしました。なので、もう時間が本当に足りないぐらい、色々と話したいことがあります。
(終了するというタイミングで)あ、映画『羅生門』が大好きです!
(会場笑い)