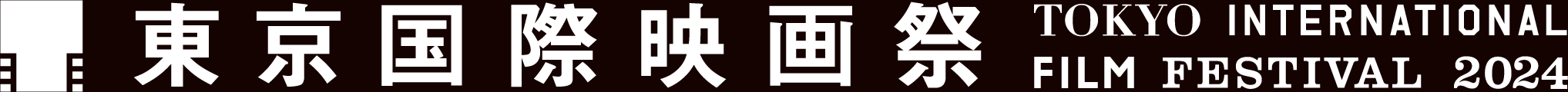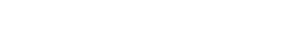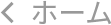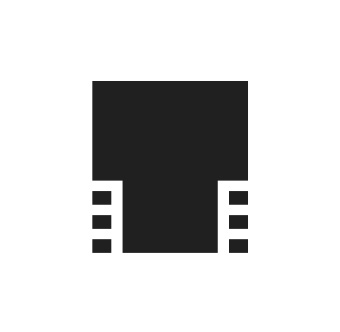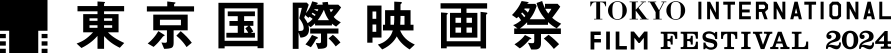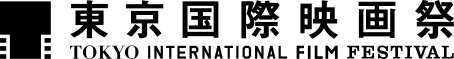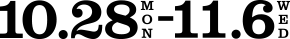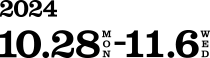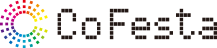東京国際映画祭公式インタビュー 2024年10月29日
コンペティション
『わが友アンドレ』
ドン・ズージェン(監督)、リウ・ハオラン(俳優)、イン・タオ(俳優)

父の葬儀に出席するため飛行機に乗ったリー・モー(リウ・ハオラン)は、機内で中学時代の親友アンドレ(ドン・ズージェン)と出会う。不思議なことにアンドレは自分を覚えておらず、リー・モーは記憶を無くした親友と郷里までの道のりをともに歩むことになるが…。
2012年、初主演映画『青春派』で映画デビュー。中国で一躍人気者となり、ジャ・ジャンクー監督の『山河ノスタルジア』(15)『長江哀歌』(18)を経て、昨年TIFFで上映された『平原のモーセ』に主演、『アートカレッジ1994』にも声の出演を果たした若きカリスマ俳優、ドン・ズージェンの初監督作。
中国の現代小説家シュアン・シュエタオ(『平原のモーセ』『ゴッドスレイヤー 神殺しの剣』の原作者でもある)の短篇小説を、ペマ・ツェテン作品で知られるリュー・ソンイェの撮影、ウォン・カーウァイの衣装デザイナーにして映画編集者としても名高いウィリアム・チャンを編集に従えて映画化。わずか30歳にして自らのスタイルを持つ、堂々たる作風を披露している。
東京でのワールド・プレミア上映に来てくれた監督、親友でもある「唐人街探偵」シリーズのスター、リウ・ハオランさん、テレビの世界で軒並み演技賞を受賞してきたイン・タオさんが取材に答えてくれた。
──昨日のワールドプレミアの感想をお聞かせください。
ドン・ズージェン監督(以下、ドン監督):作品を観客に観てもらうのはこれが初めてで、観客と一緒に映画館で観るのも初めてだったので、新人監督としては観客の反応がとても気になりました。

イン・タオ(以下、イン):じつは、他の編集版は見たことがあるのですが、完成版を見たのは今回が初めてです。監督が編集をするたびに映画の雰囲気が変わるので、楽しんで見ることができましたし、観客がどう反応するかドキドキしながら見ていました。

リウ・ハオラン(以下、リウ):映画館で観客と一緒に自分の映画を観ることに、あまり慣れていないんです。観客の反応が気になって、作品に集中できないんですよね(笑)。
昨日初めて作品を観て、すぐにのめり込んでしまいました。作品の中で大きな割合を占めている子ども時代のパートをようやく観ることができて、私たちの子ども時代を演じてくれた10代のふたりの俳優の演技にあっという間に引き込まれてしまいした。

──俳優としての経験は、今回、監督をするにあたってどう役立ちましたか?
ドン監督:具体的に何がどう役立ったのかはよくわからないのですが、私にとって、原作小説を読んで脚本を書いて撮影し、ポストプロダクションを行うまでのすべての工程は、とても自然に進んだことでした。どの映画が私を助けてくれたとか、どんな経験が私を助けてくれたということはあまり考えてはいません。人生におけるすべての経験が私を助けてくれていると思います。
──映像スタイルについてはどんなことを心掛けましたか?
ドン監督:長い期間をかけて脚本を書いたので、脚本のスタイルは毎年変わりました。今の撮影方法を確立したのは、最後にロケハンをした時でした。カメラマンが優秀で、よき友人だったことも幸いしました。暗黙のうちに私たちは互いを理解し合える関係にあり、映画のスタイルも、ふたりの直感を頼りにスタイルを磨いていきました。
──友情を描く映画は現在進行形のものが多い気がしますが、この作品は回想形式を採用して内省的です。
ドン監督:これもまた、自分の感覚に基づいてそのようにしました。小説は主に子どもの頃の物語が描かれていますが、脚本を書く際、自分の子ども時代を思い出し、どんな断片的な記憶にも強烈な色彩があることに気づいて、その眩さを取り入れていきました。
──リウ・ハオランさんはずっと感情を溜め込む役柄ですね?
リウ:大人になるということは苦しいことです。アンドレがリー・モーを認識してないだけではなくて、リー・モーもアンドレの記憶が曖昧です。
子ども時代をともにしたふたりはずっと疎遠でいましたが、ある日突然、様変わりしたアンドレが現れます。アンドレは隠し事を抱え、大人になるにつれ大きな感情の変化を経験しました。この変化を劇的に伝えるために、僕は撮影前に監督と何度も話し合い、疎遠だったふたりが出会う瞬間の互いの感情を深く掘り下げました。
──監督自身が演じるアンドレはエキセントリックな役柄です。
ドン監督:実際、アンドレはとても興味深く、複雑なキャラクターだと思います。ここにいるタオさんも脚本を読んで「アンドレは難しい役柄ですね」と言っていたのを覚えています。ただ、本当に長い時間をかけて私はこの脚本を書き、彼に寄り添い続けたので、ごく自然に演じることができました。
とはいえ、監督しながら自分で演じるというのはどうにも不思議な感覚で、モニターを見ていると、自分をどう調整したらよいのかわからなくなることがありました(笑)。
子ども時代のアンドレが才能のある特異な子なのは、子ども時代は誰にとっても特別であることと軌を一にしています。大人になると誰もが普通になってしまう、そういう部分もアンドレには投影してあります。
──子ども時代のリー・モーのお母さんを演じたイン・タオさんは、憂いを帯びた瞳が大変印象的でした。
イン:彼女は夫との関係で問題を抱え、誰に相談すればいいかもわからない。その悲しみを表現することに専念しました。
──時間軸を越えたラストが印象的です。
ドン監督:アンドレは私の感覚の結晶だから、あれが唯一の選択でした。
──監督とリウさん、ふたりの友情や子供時代の記憶も反映されている?
ドン監督:親友をテーマとする作品を親友と作ることができたのは、大変貴重で素晴らしい経験でした。小説はもっぱら子どもたちの話で占められているので、そのまま映画にする選択肢もあったのですが、私たちはもう一歩踏み込んで、ふたりの個人的な感情も交えた物語に仕立てました。

リウ:僕は数年前に大学を卒業したばかりで、成長するということがどういうことなのか、まだよくわからないことも多いんです。ただ撮影中に頭に浮かんだのは、突然連絡もなく消えた親しい友人の面影でした。その悲しみがあったので、リアルな感情を役に投影することができたと思います。
ドン監督:悲劇の多くは、我々が気づかなかった事実から起こる。私とリウは映画を作る過程でそのことを徐々に学んでいきました。

インタビュー/構成:赤塚成人(四月社)