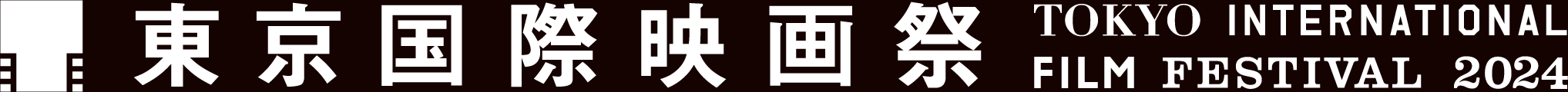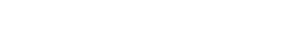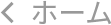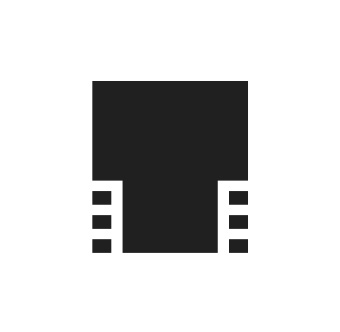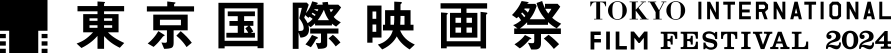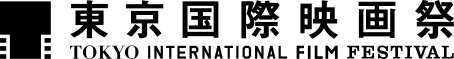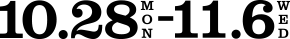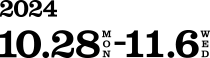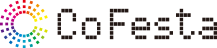東京国際映画祭公式インタビュー 2024年10月30日
コンペティション
『チャオ・イェンの思い』
ミディ・ジー(監督/脚本/編集)、チャオ・リーイン(俳優/チャオ・イェン役)

辺境地で生まれたチャオ・イェンは、今や映画やドラマで引っ張りだこの大スター。そんな彼女のもとに匿名の脅迫状と、長年音沙汰がなかった姉の来訪連絡が。久しぶりの再会に心躍ったのも束の間、チャオ・イェンがひた隠しにしてきた過去が、彼女のキャリアと姉妹関係を脅かすことに…。
台湾をベースに活躍し、2014年の『Ice Poison』が第87回アカデミー賞外国語映画賞(当時の呼称。現在の国際長編映画賞)台湾代表として選ばれたミディ・ジー監督。そんな彼が長編6作目に選んだ題材は、原作ものだ。それがジャン・ユエランの小説「大喬小喬」をもとに、彼が監督・脚本・編集を担ったサスペンスフルなヒューマンドラマ『チャオ・イェンの思い』。監督とチャオ・イェンを演じたチャオ・リーインに話を聞いた。
──新作の企画に原作ものを選んだ理由、そして原作小説「大喬小喬」との出会いを教えてください。
ミディ・ジー(以下、ミディ監督):ジャン・ユエランさんの原作小説を読んだときに、女性の視点で様々なことを描いていたところにすごく興味を惹かれました。この主人公、チャオ・イェンは、中国の辺境から都会に出てきて、そこで必死に自分が求める人生を追求していき、自分を抑圧してきた環境や人に対し「絶対負けない」と対抗しています。抗い、自由を求める女性の姿を描いているのがとても気に入り、映画化を決めました。それに、このチャオ・イェンと私の家庭環境が似ていたことも映画化を決めた要因になっています。
私は女性が強い家に生まれたんです。母が一家の大黒柱として家族を支え、上の姉も母と同じように非常に強い女性で、頑張って私たちを養ってくれました。また、私もチャオ・イェンと同じように片田舎から出てきて一生懸命人生を切り開こうと奮闘してきたことも大きいですね。女性の視点で描くことや、チャオ・イェンの生き方へのシンパシーが、本作の映画化を突き動かしました。

──チャオ・リーインさんは、キャスティングの前からこの小説をご存じでした? また、キャスティングのプロセスで印象に残っていることはなんでしょう?
チャオ・リーイン(以下、チャオ):このお話をいただく前から、原作を読んでいました。私も監督と同じく、とても繊細な文章で女性の視点が描かれていることが気に入っていたんです。そんなときに、監督からお話をいただきました。思い入れのある小説なので、どのように女性の視点を映像化するのか、監督とよく話し合ったことが印象深いですね。そのディスカッションで、この役は私にとってもチャレンジになると思い、出演をお受けしました。

──お話が来る前から注目していた原作とは、ちょっとした運命ですね。
チャオ:そうなんですよ。原作を読んだときは、主人公が家族とどう折り合いをつけながら生きていくかとても興味がありました。女性が独立して生きていく過程には、いろんな困難があります。でも、それを乗り越えて自由を得るという主人公に、とても共感したんですね。キャスティング時にお話をうかがっていて、監督は女性の生き方をじっくりと見つめてきて、齟齬なく描かれる方だと思ったんです。
──では、監督がチャオさんを主演に決めた理由は?
ミディ監督:チャオ・リーインさんは、今までたくさんの作品で豊かな演技を見せてきたスター俳優です。そんな彼女に、現代で生きる女性をテーマにした物語で、また別の顔を見せていただきたいと思ったのが第一要因です。
また、当然のことながら、彼女の演技は素晴らしいと思っており、彼女の芝居の力が必要だったのです。なぜなら、チャオ・イェンというのは非常に複雑な人物で、戦う相手がいっぱいいる特殊なキャラクター。それをオーバーに表現するのではなく、抑制の効いた芝居で自分の中にこもった感じで演じてほしいと思っていました。写実的な描き方ではなく、できるだけ自然な感じで誰かにやっていただきたかった。そこで彼女が適役だと思ったんです。
──原作を120分弱の映画の脚本に落とし込む作業はものすごく大変だったと思います。
ミディ監督:脚本を手掛けたのは私と原作者のジャン・ユエランさんに加わってもらいました。彼女が加わることによって、役者の芝居に様々なプレッシャーを与えることができると思ったからです。小説を映画化するときには、一旦小説の存在を燃やしたほうがいいと思っています。小説を脚本にするときには、その作品が持っている魂、精神を拾い上げて作ることから始まると考えているので、ストーリーそのものを追うことが大事ではないのです。
ただ、この作品の場合、女性が光に向かって生きていくことを描く映画にしたかったので、原作の中で「奮闘する女性の視点」は削りたくありませんでした。実はこの原作は、主人公のお姉さんは自殺してしまうという結末で悲惨なんですよ。現代の女性を描くにあたり、それだとあまりにも悲惨なので、結末は変えています。
──チャオさんも監督同様、原作がお気に入りだっただけに、脚本と原作の違いは感じられていたと思います。脚本を最初に読んだときはいかがでしたか?
チャオ:私も原作の結末に疑問があって、映画にするときは主人公が現代社会の中で頑張っている姿を明るく描いた方がいいんじゃないかと思っていました。脚本を読んで、私の考えと同じく、監督はそのように描いてくださる、と感じました。
──撮影前後で、おふたりのディスカッションはどのようなことを?
ミディ監督:どうやったらここがリアルに撮れるか、技術面のことを中心に話し合いました。また、私が映画を撮る時の習慣として、脚本に基づいて撮ること、そこにより即興性を加えていくことを大事にしています。今回は現場で、チャオ・リーインさんが色々と良いアイデアを出してくれました。
ひとつ例を挙げるとすると、冒頭の服装。あれはフードつきの上着ではなく、普通のカーディガンなんです。それをわざとあのように被ったのは、物語のなかにある主人公のいろんな秘密をあの中に閉じ込めるという比喩になる、と。スタイリストが思いつかないようなことを彼女が思いついてくれました。じつは、冒頭のシーンで、チャオ・イェンが持っている神秘性、そしてこの映画自体が持たなければならない神秘性を、どのように表現すべきか私は非常に悩んでいたので、非常に助かりました。
また、チャオ・イェンがおばあさんの店に麺を食べに行くシーンでも、彼女から提案がありました。おばあさんはちょっと黒社会に関わっているような役として描いていますが、あそこでおばあさんとチャオ・イェンは殺人について特に話し合いません。彼女は「大スターであるチャオ・イェンは、たとえ黒社会の人相手でも殺人のことを直接言わないのではないか」、「食べ物を話題にする方がよりリアルな感じで撮れるのではないか」と言ってくれたんです。
──チャオさんご自身が大スターだから言えたことですね。
チャオ:(笑)。殺しの話より、ぼかした方がより面白いんじゃないかと思ったんですよ。
──ご自身でご提案したフードもそうですが、この作品のあなたの役は衣装のパターンが多いですよね。役作りを衣装に助けられたエピソードがあったら教えてください。
チャオ:役者にとって、衣装は役作りにとても大きな手助けをしてくれますが、本作ではそれがかなりありました。チャオ・イェンの私生活は冷たく寂しい感じなので、全体的に黒を基調とした服を着ています。ですが、劇中劇では色味が多い服。それは自分が劇中劇で演じているところの社会環境、背景が違うからです。それが変わるのがラストのミャンマーのシーン。彼女の洋服にはいろんな色が使われていますよね。
ミディ監督:ミャンマーでのシーンで鮮やかなスカートにしたこと。これはやっぱり重要ですよね。先ほどから何度も申し上げている、冒頭で頭からかぶっている服はとても地味ですが、その色で頭からかぶっているというのが、あのシーンにとても力を与えており、対比になっていると思います。
──映画の3分の2まで行かないとタイトル出てこない大胆な構成ですが、あれは脚本上で決まっていたことでしたか?
ミディ監督:決めていました。タイトルは81分のところで出していますね。全編が112分なので、おっしゃる通り大体3分の2の辺りです。脚本を何行か書いたらロケハンをし、何度も何度も改稿し、最終的な撮影台本はクランクインの1か月前くらいにできましたが、そのときからこの構成です。タイトルを出したところで描いているのは、主人公姉妹が雲南省で父親と暮らしている回想。主人公は大人になっても父の死に対して大きな罪悪感を持っているため、あのシーンの切り替えで「主人公が父を迎えに行く」というイメージを持たせたかったからなんです。そのシーンの後は子どもが生まれるシーン。父の死の次に子どもが生まれる…新しい命が育っていくということを表現するために、この構成になりました。

インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)