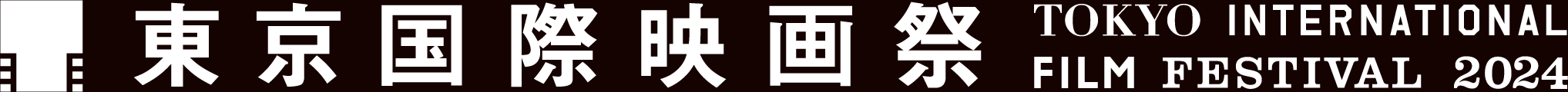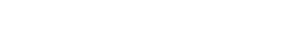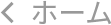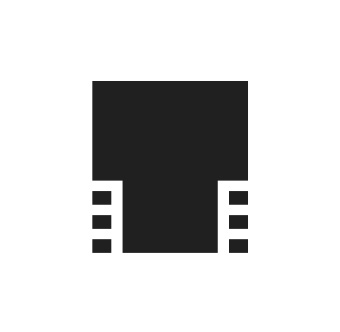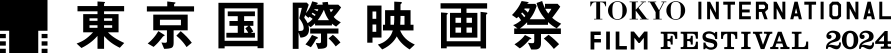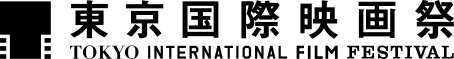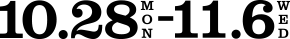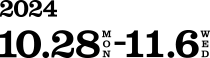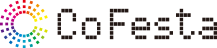ジェイラン・オズギュン・オズチェリキ監督(左)、ゼイネップ・セジルさん(右)
11/2(土)ウィメンズ・エンパワーメント『10セカンズ』上映後に、ジェイラン・オズギュン・オズチェリキ監督、ゼイネップ・セジルさん(撮影監督)をお迎えし、Q&Aが行われました。
ジェイラン・オズギュン・オズチェリキ監督 (以下、監督):今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。(撮影監督の)ゼイネップと私は、この映画祭に来るのは初めてですが、(参加することができて)とても幸せに感じています。私も映画を観ていましたが、どちらかといえば観客の皆さんを見ていまして、東京国際映画祭には本当にすばらしい観客の方々が参加されていると思いました。お辞儀してありがとうございますと伝えたいぐらい、世界一の観客ではないかと思いました。
ゼイネップ・セジルさん(以下、セジルさん):呼んでいただき、本当にありがとうございました。この映画祭に本当にワクワクしています。皆様が映画を楽しんでくださったことを願っています。
アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ シニアプログラマー(以下、ツヴェトコビッチSP ):トルコからお越しいただいて、本当に感謝しています。私はマケドニアの出身で、トルコから遠くありませんが、この夏、マケドニアからトルコに行く途中の飛行機でこの映画を拝見しました。とても面白い、オリジナルのサイコスリラー、心理的な要素のある物語だったと思います。
監督はテレビなどでも活躍されていて、映画も撮っていらっしゃいますが、最近はサイコスリラーや心理的な要素のあるものに傾いている気がします。この映画は、母性の問題、教育システムの問題、社会格差の問題、キャンセルカルチャー(著名人・企業などに対するボイコット・バイコットなどの運動)の問題などが絡んでいます。こうしたことを踏まえて、どうしてエルディ・イシュクさんの舞台脚本を選んだのかお伺いしたいです。
監督:私は脚本も書いており、監督、共同プロデューサーとしても活動しています。 フィクション、ドキュメンタリー、映画、長編映画など、いろいろと作っていますが、全てに共通している要素は、「記憶」と、「観客が主役の気持ちになって、主役の心情に観客を取り込めるか」という点です。
この映画の(原作)脚本は元々、7年前の2020年に始まった舞台劇でしたが、コロナの影響で5・6回打ち切りになってしまいました。そこで、その脚本を書いたエルディ・イシュクさんが、私の映画を観て「(自分の作品を)映画にして欲しい」と話をもちかけてくれたのです。
ご覧いただいたように、物語は、1つの部屋の中で全てが進行するという構成になっていて、それを映画にしようと思いました。元々が舞台劇なので、芝居の上手な女優さんを2人集めなければいけないと思いました。その時点では、脚本は草案状態でしたが、主役の女性2人と、脚本を書いた、エルディ・イシュクさんの4人で、4カ月の間打ち合わせを行いました。
舞台と同じようなアプローチをしましたが、リハーサルには4か月もかかってしまいました。キャラクターに深く入り込む必要があったからです。主役の2人と私の、3人でリハーサルを4カ月重ねましたが、当然、その間に脚本が何度も変化しました。最終的には、私と俳優を含めた6人で脚本を作り上げたかたちになりました形になりました。
脚本には、私自身も母親なので、母親としての立場上の問題も、脚本にたくさん取り込みました。
ツヴェトコビッチSP:この作品のオファーがあった時、(セジルさんは)どう思われましたか。男性が指示するような男性メインの現場と、女性監督がいる現場で何か違いはありましたか
セジルさん:私にとって初めての映画ですので、男性監督の撮影現場を経験したことはありません。初めての映画撮影でしたが、監督と仕事ができてとても良い経験になりました。 監督は欲しいものがはっきりしていますし、イマジネーションも素晴らしいです。ですから、監督が見ている世界を一緒に見ようとしました。本当に良い経験でしたし、やはり女性同士なので話しやすかったです。お互い、同じようなことを感じて気持ちをシェアできます。友情も芽生え、とてもありがたい経験でした。
監督:撮影監督のセジルさんは、映画業界で10年間アシスタントカメラマンとして仕事をされていました。基本的に、男性であれば、5年もアシスタントをすれば必ず撮影監督になります。彼女は、“女性”であるために10年もかかってしまった。これは、映画業界に蔓延る問題だと思います。
──Q:主演の2人をキャスティングした理由と、演技に関して指示されたことについて教えてください。
監督:この映画自体、脚本家であるエルディ・イシュクの夢だったので、やはり、彼を尊重して、どのような役者を使いたいか彼に聞きました。すると、彼がキャストの候補者リストを提示してくれました。母親役の方は、トルコのトップスターです。テレビメインですが、舞台でも活動されています。ただ、映画は今回が初めてでしたが、やってみようとなりました。
リハーサルを4か月したと申し上げましたが、最初の1か月は心理学者の方に(リハーサルに)入っていただきました。最初に、母親のキャラクターに関して心理学者の方に入っていただいたんですね。この作品の母親は、境界線のギリギリにいるような人物で、彼女が部屋に入ると(部屋の中にいる)みんなピリッとしてしまう。子どもでさえも、お母さんに常に注意を傾ける必要がある、危険な存在です。ですので、心理学者の方に入っていただき、いろいろなお話を伺いました。
実際にあったエピソードをたくさん教えてくださいましたが、そのなかに、この映画に出てくるような、子供との間に少し壁があったり、汚い言葉や暴言を吐いたりするようなお母さんが、何も言わずにドアの前で子どもの帰りを待っていたという話がありました。そのお話を聞いて、これは使えると思い、脚本に追加しました。
──Q:映画の中盤に、上下逆になる映像が使われていますが、セジルさんのアイデアでしょうか。
セジルさん:上下逆になるシーンですね。白黒のチェスゲームのような床を見せて、部屋全体を見せたいと考えていましたが、私の判断というよりも、編集の段階で監督がそういう風にしようとおっしゃいました。
監督:あのシーンはターニングポイントです。あのシーンで、カウンセラーもこの母親はおかしいと気づきます。お母さんも、娘は自分に危害を加えるかもしれない、と気付きます。母親も、今までの自信がなくなって、弱い部分が露呈する様子を表現したのです。