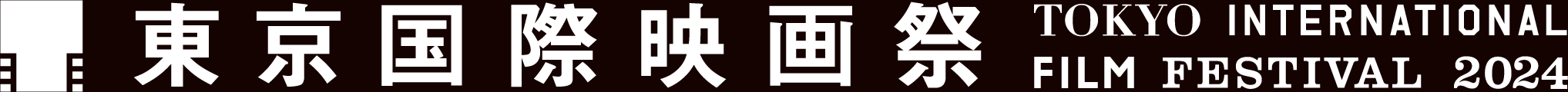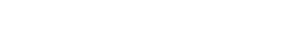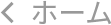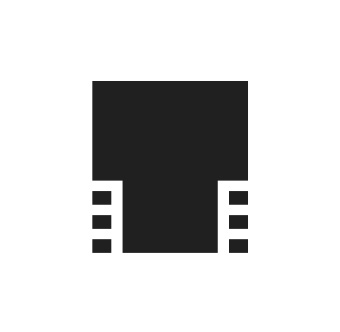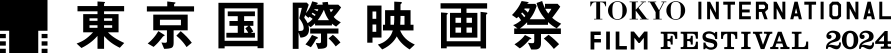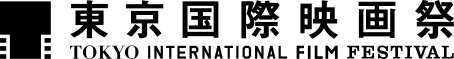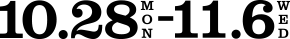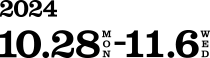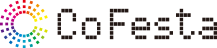10/30(水)Nippon Cinema Now『レイブンズ』上映後にマーク・ギル監督、フェルナンド・ルイスさん(撮影監督)をお迎えして、Q&Aが行われました。
市山尚三プログラミング・ディレクター(以下、市山PD):ゲストの皆様、最初に一言ずつご挨拶をお願いいたします。
マーク・ギル監督(以下、監督):こんばんは、私はマークです。この場に立つことができ、大変光栄に思っております。この舞台に立つことをあまりにも長い間夢見ていたと言っても過言ではございません。ですから、今回このように上映させていただくことを大変光栄に思っていますし、御礼を申し上げます。また、客席にはキャストやクルーの方々もいらっしゃいます。そうした皆さんなくしてはこの映画を作ることはできませんでした。
フェルナンド・ルイスさん(以下、フェルナンドさん):私からも御礼を申し上げます。私にとっても、今日は夢が叶った日だと言っても過言ではありません。この場に立つことができ、本当に嬉しく思っております。皆様もお越しいただきまして本当にありがとうございます。
市山PD:それでは、最初にまず私から監督に1つ質問をさせていただきます。
この作品では、日本でもこれまで映画になっていなかった深瀬昌久さんというカメラマンにスポットを当てた素晴らしい作品に仕上がっております。
監督はイギリス・マンチェスター出身とのことですが、なぜこの深瀬さんという人物に興味を持ったのか、そしてどのようなプロセスでこの撮影を実現させたのか、監督にお話を伺いたいと思います。
監督:私は日本の写真だけではなく、日本の文化や日本そのものが大好きなんです。イギリスでも、森山大道さん、荒木経惟さん、石内都さんといった日本の写真家の方々の名前を耳にしたことはありましたが、深瀬昌久さんのお名前は知らず、たまたまイギリスの新聞に彼の記事が載っていて、そこで初めて深瀬さんのことを知りました。私は、「鴉(RAVENS)」(以下、「鴉」)という彼の写真集を、この30年間で最も重要な出版物の1つだと考えており、素晴らしい本だと思っています。
先ほど申し上げた新聞記事には、深瀬さんだけではなく奥様の洋子さんについても触れられており、お二人のラブストーリーに大変感銘を受け、興味を持ちました。ただ残念ながら、当時、今から10年ほど前では、深瀬さんに関する資料をなかなか探すことができませんでした。それでも、Masahisa Fukase Archivesなどのサイトも活用しながら様々な資料を集めたのですが、その時私は別の映画の制作に取り組まなくてはならず、撮影ができなかったのです。その後、別の作品の制作を終えた2019年から、ようやく本格的に本作に取り組めるようになりました。
深瀬さんは天才であると同時に、強靭な素晴らしい写真家です。そうした評価は、決して私だけのものではなく、他の方々に聞いても、深瀬さんは最高の写真家の第一候補に上がるほど、彼の評価は高いんです。
しかし、なかなか深瀬さんは(写真界以外の)他の分野の方々に広く知られているわけではないように思いました。そのため、彼をきちんと世の中に知ってもらう時代が来てもいいのではと思いました。
──Q:主演の浅野忠信さんと瀧内公美さんをキャスティングされた理由と、実際にお仕事をご一緒されてどのように思われたか、聞かせてください。
監督:私は『殺し屋1』で初めて浅野忠信さんを拝見し、その場で彼に恋に落ちました。ですので、深瀬さんの役は彼に演じていただきたいとずっと思っていて、脚本が出来上がってすぐに浅野さんにオファーしました。正直、もし浅野さんが承諾してくださらなければ、この映画は撮らなかったでしょう。それぐらい、ぜひ彼に演じてほしいと思っていました。
そして、洋子役の瀧内公美さんは、本作のプロデューサーを務めてくださった石井恵さんとキャスティングディレクターの方が探してくださいました。私自身、実際の洋子さんとは長い時間を一緒に過ごし、よく存じ上げていたのですが、残念ながら、彼女を映画の中で演じられる女優さんを思いつきませんでした。洋子役を探すにあたりどうしようかと悩んでいましたが、たまたま『火口のふたり』を拝見したところ、瀧内さんがとても勇敢な演技を見せており、ぜひ洋子役にオファーしたいと感じました。
──Q:主人公の男性は、死に対する願望のようなものがあったのでしょうか。
監督:時にはあったのではないかと思います。彼の死に対する考え方や哲学というのは、彼のお父さんに由来していると考えています。彼は、どこかで、死という概念を超越しようとしていたのではないかと思っており、彼は写真によって「瞬間」をとらえることで、概念的に死を回避できると思っていたのではないかと考えています。 だからこそ、彼は、洋子さんや家族、猫の写真を撮影することで死を欺こうとしていたし、同時に、写真を撮るという行為が彼にとっての唯一の愛情表現だったのではないかとも思います。
──Q:なぜこの映画の中にややグロテスクな「クリーチャー」を登場させたのでしょうか。あの「クリーチャー」が登場しなくても物語は展開できたと思いますし、その必然性がどこにあったのか、私なりにいろいろ考えましたが監督の意図をお伺いしたいです。そして「クリーチャー」だけ英語を使いますが、違う言語を使った意図についてもお聞かせください。(上映は日本語音声・英語字幕)
監督:あなた(質問者)の考えを、ぜひ先にお聞きしたいです。
質問者:素直に感じたのは「カラス=Raven(レイブン)」ということを意味していると感じました。Raven自体は動物(カラス)なので、本来は人間の言葉を話しませんが、それでも主人公・深瀬と心がつながって何らかの形でコミュニケートできる、という実体を登場させたのではないかと考えました。
監督:かなり詳しく深瀬さんのことを調べた結果わかったことなのですが、彼は酔うとすごくおしゃべりになったようです。一方で、お酒を飲んでいないととても無口な方とも伺いました。そうした情報から、深瀬さんが誰かと話をするということを特徴的に描写したいと思いました。
そして、もうひとつには、「カラス=Raven」は彼の性格、人格も表しているのではと思いました。そして、(質問者は)クリーチャーと仰っていましたが、私にとってはとてもセクシーだと思っていました。
あえて英語を使っている理由ですが、深瀬さんは戦争が終わった時代に生きた世代でした。日本は戦前は反米でしたが、戦後、急にアメリカの文化や音楽、食べ物に傾倒するという変化が一夜にして起きます。深瀬さんも何らかの形でアメリカに対する憧れを持っていたと思っており、そうしたことを、英語で話すRavenに投影する、というのが私の中でのアイデアでした。そして、Ravenはジョーカーのような役どころも担っていると考えています。
──Q:どのようにこの映画のためのリサーチをなさったのでしょうか。特に、実際の洋子さんとお会いになってどのような時間を過ごされたのか、そして、どのように彼女にコンタクトをしてアプローチしたのか、教えてください。
監督:やはり、写真からリサーチを始めました。この映画のために参考にした写真集が3冊あります。「家族(FAMILY)」、「洋子(Yohko)」、そして「鴉」を参考にしました。加えて、彼が書いたエッセイがいくつもありますので、それを英訳してもらいリサーチしました。 そして、日本政府機関による資料協力も得ることができましたし、Masahisa Fukase Archives の方々にも本当に多大な協力を得ました。
石内都さんなどに協力を得て、最終的に妻の洋子さんにたどり着き、実際にお会いすることができました。実際に彼女とお会いした時、やはりこの映画、そして深瀬さんの作品、人生は、洋子さんなしでは語れないと思いました。彼の人生は、洋子さんが大部分を占めているので、洋子さんのことを知ることは不可欠でした。
彼が撮った洋子さんの写真は本当に素晴らしく、そして彼女を失った(離婚した)後に作った「鴉」も、彼女がいないからこそ、かえって素晴らしい作品が完成したと思います。しかし同時に、そこには洋子さんが確実に存在していて、だからこそ「鴉」が生まれたわけです。そうした意味でも、洋子さんは、彼の元を去った後にも多大なる影響を与えていたので、色々とお話を伺うことができて、大変幸福でした。
私の印象としては、洋子さんは大変頭のいい方です。 最初にお会いした時に、「なんで映画を撮りたいの?」と聞かれました。 少し不信感を抱いてらっしゃるのかと思ったので、一生懸命コツコツと信頼関係を築いていき、いろいろなお話をさせていただけました。
深瀬さんがもたらしてくれたご縁かなと思ったのは、なんと、私の誕生日と洋子さんの誕生日が同じ日なのです。 洋子さんは、(最初)それを信じてくださいませんでした。そこで、私が自分の運転免許証を出して。彼女も自分の古い運転免許証お持ちで、お互い(免許証を)見せ合って、同じ日ですね、と。深瀬さんが取り持つご縁なのかな。このようなご縁を感じる出来事は、この映画を作っていていくつかありましたが、これは、その中の1つです。
市山PD:最後に、フェルナンドさんに1つお伺いしたいと思います。フェルナンドさんは、日本での撮影は今回が初めてでしょうか。
フェルナンドさん:はい、日本での撮影はこの作品が初めてです。
市山PD:ヨーロッパでの撮影等と比べて何か難しかったことはありましたか。
フェルナンドさん:今回の撮影は、私にとってこれまでにないぐらい、最高に素晴らしい経験でした。私はいろんな撮影部で働いてきましたが、今回がベストと言っても過言ではありません。 それはやはり、日本スタッフの素晴らしさだという風に思うんです。日本のスタッフと初めて一緒にお仕事をさせていただいて、 彼らの熱心さ、細部まで入念に考えて、そして気を遣って、撮影が潤滑に進むようにしようという気持ち、そうしたものは他に類がないほど素晴らしいものでした。 監督は別ですが(笑)。撮影スタッフもそうですし、プロダクションチームは本当に素晴らしかった。私は毎日仕事に行くのが幸せでなりませんでした。
そして、マーク・ギル監督は、真のコラボレーターです。 私がどんなアイデアを持っていっても、それが悪いものであっても耳を傾けてくださいました。私が自分のアイディアを彼とシェアしやすいように、常にオープンでいてくださいましたし、これは私だけにではなくて、他の人に対してもそうでした。彼の元で仕事ができた私たちは、本当に真の意味で1つのファミリーでした。エゴを持って1人でなにかをやろうというものはなく、一致団結して、スタッフが力を合わせてできたセットだったので、素晴らしいセットになりました。
市山PD:この作品は、2025年3月にTOHOシネマズシャンテ、新宿武蔵野館、ユーロスペース他にて、全国公開となります。ぜひともお知り合いの方にお薦めください。また、ぜひまたもう一度劇場でご覧、ご観覧いただければと思います。
今日はありがとうございました。