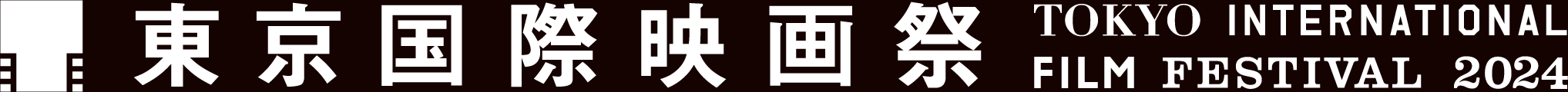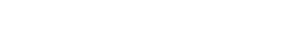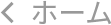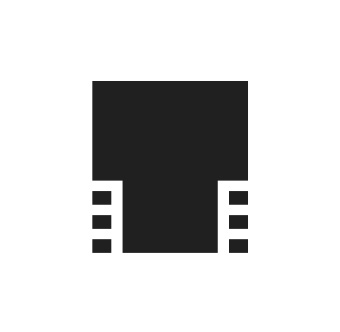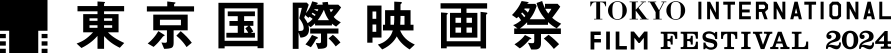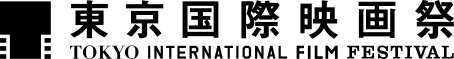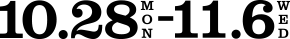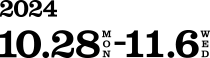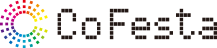東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月1日
コンペティション
『彼のイメージ』
ティエリー・ド・ペレッティ(監督/脚本)、クララ=マリア・ラレド(俳優)

コルシカ島の地方紙で働く写真家アントニアが交通事故で亡くなった。若い頃から写真を撮るのが好きだった彼女は、18歳の時にコルシカ民族解放戦線の活動家パスカルと恋に落ちた。しかし活動は激化するいっぽう。逮捕と釈放を繰り返すパスカルとの生活に閉塞感と限界を感じたアントニアは、戦場カメラマンとして紛争地へ旅立つが…。
『Undercover』で2021年サン・セバスティアン国際映画祭最優秀撮影賞を受賞したティエリー・ドゥ・ペレッティ監督の4作目。2024年カンヌ監督週間の入選作でもある本作は、同じコルシカ島出身の作家、ジェローム・フェラーリの小説を映画化。独立運動に揺れるコルシカ島の80年代から20年におよぶ激動の歴史を背景に、女性写真家の濃密な人生を浮き彫りにしていく。
『愛する者よ、列車に乗れ』(98)などで俳優経験もあるティエリー・ドゥ・ペレッティ監督、本作が初の演技経験ながら、主人公アントニアの20年間を演じきったクララ=マリア・ラレドにお話を伺った。
──原作との出会いと映画化に至った経緯は?
ティエリー・ドゥ・ペレッティ(以下、ペレッティ監督):原作のジェローム・フェラーリと私はほとんど同世代。彼の作品が最初に出版された頃に、私も映画を撮り始めました。同じ時期にキャリアをスタートしていますから、個人的な知り合いではないけれど、お互いの存在は知っている関係でした。私としてはいずれ彼の作品で何か撮りたいと思っていました。そうこうするうちに、彼がゴンクール賞(フランスで権威ある文学賞)を受賞して、注目されて映画化権が飛ぶように売れてしまい、私の手にはなかなか入らなくなりました。
そんな私の思いを知った彼が、出版される前の「À son image」という本をPDFファイルで送ってくれたのです。もちろんその内容にすごく感銘を受けて「ぜひ映画化したい」と話をして、やっと映画化に至りました。

──脚本は監督とジャンヌ・アプテクマンとの共同執筆ですが、原作を脚本に書き換えるにあたりどんな点を意識しましたか?
ペレッティ監督:小説をそのまま映像化したのではなく、それを素材として映画を作ることにしました。原作に書かれた人物やエピソードから思い浮かぶシーンの数々を連ねていく。脚本は原作とは違うバージョンのつもりで書いていきました。その作業のなかで最も重要なのは登場人物の描き方。俳優さんたちが登場人物を生身の人間として演じられるかを常に意識していました。ですからキャスティングは非常に重要でした。
幸いクララ=マリアがアントニアを演じることになったので、彼女がどういう声で、どういうリズムで喋るのかを考えながら、最終的に脚本を仕上げました。原作とこの映画の大きな違いは、原作のほうが政治運動や闘争により批判的な部分がありますが、私はあまり批判的なメッセージを込めてはいません。
──アントニア役にどのような経緯でキャスティングされましたか?
クララ=マリア・ラレド(以下、ラレド):もともとティエリー監督の『Undercover』に対する批評コラムなどを、コルシカの機関紙に投稿したりしていました。それを知っていた友人から「新作のキャスティングをしているらしい」と聞いたので、挑戦してみました。「これは賭けだ!」と思っていたのですが、良いご縁があってキャスティングされました。

──役作りはどのように?
ラレド:アントニアという女性はとても複雑なので、彼女がどういう視点や思考で世の中を見ているかを理解しなくてはいけない。しかも彼女はカメラを通しても世界を見ている。その場に居ながらもちょっとプリズムみたいな、物事を二重の視点で見ている感じがあるので。
まずはカメラがどういうものかを理解するために、撮影当時は大学生でしたが写真のレッスンを受けて、アニエス・ヴァルダの写真学校にも通って、撮るだけではなく現像技術も学んで。実際にデモの現場でも撮影したりして、アントニアがどういうふうに物事を見て撮っていたのか、なぜカメラが好きだったのかを体感できるまで、とことん役作りをしました。
──18歳から30代後半まで、20年間を演じるための外見的な役作りは?
ラレド:素晴らしい監督の演出のお陰ですね。自分では意図的に何かをした感覚はありませんでした。表面的な変化よりも、その時々のアントニアの中身を体現することが大切だと思って演じていたので。空間と場所とリアリティと自分をしっかり信じながら演じることで精一杯。そうすれば、自然に年齢がついてくる感じだったと思います。
──監督は、時の変化をどのように映し出そうと考えていましたか?
ペレッティ監督:撮り始める前はあれこれ考えました。世代によって俳優を変えるとか、老けメイクをしようかとか。でも結局、最小限ミニマルでシンプルにやることにしました。髪型や衣装のちょっとした変化によって時代が変わったことを感じさせることはあっても、それもほんの些細なこと。あえて目立たないようにしました。
アントニアがその時々の年齢に見えたのは、やはりクララ=マリアに柔軟性があって、役に対しての理解力が優れていたからだと思います。彼女自身も撮影が進むにつれて成長して、最後には成熟さえも感じられるようになりましたから。その成長がそのままスクリーンから感じられるのだと思います。
──コルシカなど、背景に関しては?
ペレッティ監督:半分がアジャクシオで、車で40分ほど行った僕の出身地バステリカでも撮りました。ストーリー上、セルビアのベオグラードにもロケに行きましたが。時代背景に関してもミニマルでシンプルに徹しました。時代を完全に再現することにエネルギーを注ぐのではなく、今の時代の今の話として見られるようにしようと思ったのです。
撮影場所が、アジャクシオの自分が住んでいる家の周辺や普段から行っているカフェとかばかりだったので、ホームムービーみたいな不思議な感覚もありました。
──この作品で伝えたいメッセージは?
ペレッティ監督:もちろん私自身は過激派とか暴力への不安は持っていますが、それが良いとか悪いといった特別なメッセージはありません。私にとって、ああいう時代があったという記憶が重要なのです。その記憶を呼び覚ますためにいくつかの出来事をモンタージュしながら、あの時代を映画の中で再現しているのです。
私は演劇学校には通ったけれど、映画作りに関しては独学に等しい。そこでものすごく参考になったのが、台湾のエドワード・ヤン監督とホウ・シャオシェン監督の作品です。なかでもエドワード・ヤンが監督、ホウ・シャオシェンが製作と主演を努めた『台北ストーリー』(85)、ヤン監督の『牯嶺街少年殺人事件』(91)、『恐怖分子』(86)から多くを学びました。
今回の作品もそれらの作品の影響を強く受けていると思っています。おふたりの特徴でもあるリリカル(叙情的)な雰囲気を意識して、とにかく“あの時代の記憶”をどう描くかということに集中しました。
ラレド:この映画は、ひとつの時代以上のものを映し出しています。まだ私が生まれていなくて、知らなかった頃のコルシカ島の状況が現在の政治に通じていることを巧みに描いています。コルシカ島の真実がリアルに表現されていますので、他の国の方々にもこういう歴史があったということを知っていただける。そこに大きな意味があると思っています。

インタビュー/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)