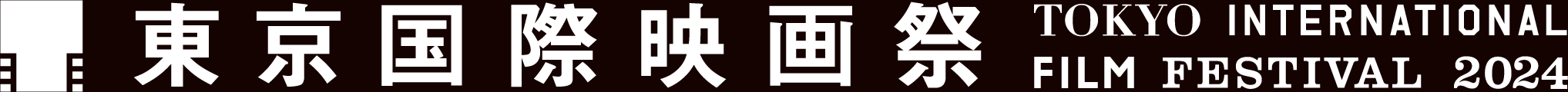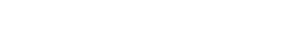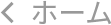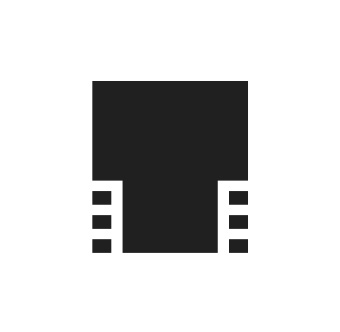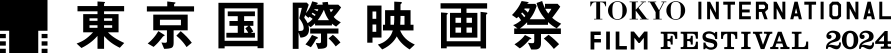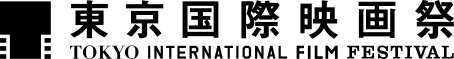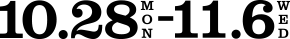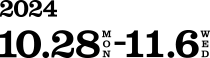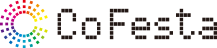東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月3日
アジアの未来
『冷たい風』
モハッマド・エスマイリ(監督・右)、モハマドマフディ・ヘイダリ(俳優・左)

雪山の登山隊が遭難し、遺体が一体発見される。担当した主任捜査官は、関係者の取り調べを重ねていくが、そのなかで別の不穏な事件が急浮上。それは遺体で発見された男の友人の妹が、15年前に焼死していたのだ。しかも、捜査の最中にもうひとりの遺体が発見され…。
殺人かそれとも事故か。いくつもの死にまつわる関係者たちが、それぞれの立場で証言を重ねていくスリラータッチのサスペンス。全編モノクロの映像で、しかも捜査官の主観ショットだけで構成された大胆なスタイルの本作は、これが初長編となるモハッマド・エスマイリ監督によるもの。複雑にからみあう事件を、ほぼひとり語りのアップで描いた意欲作。本作の舞台裏を監督、そして出演者のひとり、モハマドマフディ・ヘイダリに聞いた。
──挑戦的な脚本と撮影でした。長編1作目にしてこの作品の題材を選んだ理由、そして脚本で一番苦しんだことはなんでしょう?
モハッマド・エスマイリ監督(以下、エスマイリ監督):なかなかたくさんは読めていませんが、自分は文学から映画にアプローチしています。そのため、脚本ではまず全体のフォームに苦しみます。物語にはとにかくいろんなレイヤーがありますよね。だからこそ全体のフォームを大事に取らないといけません。そして次には、ナラティブ、ストーリーテリングです。
大事にしているからこそなんですが、本作の物語についてアイディアはあっても、それを書いたり撮ったり、というところまではいきませんでした。でも、コロナ禍がありましたから。あのとき、ポッドキャストやオーディオブックが大量に出てきたおかげで、今まで時間がなくて読んでいなかったあらゆる本を、読むのではなく聞くことで読破していきました。またそれらを聴いていると「なるほど、ストーリーを耳から聴いていると、頭の中でいろんな映像が作れるんだ」と気づいたんです。だから、もし私が映画を撮るなら、全てを観せるんじゃなくて、オーディエンスの想像に任せる映像を、という撮り方をしたら面白いかもと思ったんです。
そんな時、ちょうどアッバス・キアロスタミ監督のドキュメンタリー映画『クローズ・アップ』(90)を観たのが大きく影響しています。また、オーディオブックでは、ペイマン・エスマイリという若手の作家の小説をたくさん聴いていたこともあって、彼にアプローチしました。彼の著作の中に「スレイマンの11話」という本があります。11のエピソードで構成されたこの本は、全て役所の手紙がベースになっていて、すごく興味深い構成でした。それで彼に「あなたのこの本を脚本化して映画を撮りたい」と言ったんです。ところが彼は「難しいからやめた方がいい」と返事してきましたけどね(笑)。そこで、「自分は写真家なので、映像で説明できるから心配しないで任せてほしい」と提案。それで彼と一緒にそれをベースにした脚本を書いたんです。

──コロナ禍がなかったら実現しなかった企画だったんですね。
エスマイリ監督:そうなんですよ。
──インスパイア元があったとしても、長編デビュー作としてはかなりチャレンジの多い脚本に仕上がった思います。書き上がった脚本を映像化するには不安があったのでは?
エスマイリ監督:自分はもともと写真家なので、画にすることはできると思っていました。主にステージフォトグラファーとして写真を撮っていたので、ひとつのフレームの中で物語もキャッチしてきたんですよ。例えば、被写体にはストーリーを全部説明し、ストーリー性を持った1枚の写真にする、といった具合に。そのときの私は、1フレームを監督していたみたいな感じだったんです。イランではそういう仕事をする人はいなかったせいか評判になり、たくさんのオファーがありましたね。
1枚の写真で説明できるならば、映像としても説明できる、という自信がありました。もちろん写真と映像は違うので、普段どおりにはいかないフラストレーションはありましたし、不安になったこともあります。ですが、あることを思いついて、私のメソッドができました。それは、撮りながら編集段階までやってしまうということ。映像でもっとも大切なのはリズムです。後からポスプロで編集するのは私には難しすぎる。そこで、脚本段階から1シーンは何分になるか、オフラインの編集から始めたんです。
そうしてできた脚本は、本読みの時に役者の皆さんに渡りましたが、そのときはどのような撮り方をするか説明していません。でも、本読みの時に必ず「これは何分何秒です」ということだけは伝えていました。そこで私が考える尺どおりでなければ、少し調整をし、決定稿に仕上げていったんですね。これは役者さんたちと私の間に100パーセントの信頼がないとできないことだったと思います。
モハマドマフディ・ヘイダリ(以下、ヘイダリ):私が演じたのは、事件の証言者のひとりでアリという役。脚本を読んだときに、撮り方についてちょっと突っ込んで質問したんですが、明確な答えが得られなかったので、私は「これは映画じゃなくて舞台だな」と思うことにしました。舞台の観客の代わりに、カメラの前で全部を語る。ということは、その間にはカットが入らないということになります。セリフを全て頭に入れるんですが、1回ミスしたら最初からそのシーンを撮り直しですね。しかも1シーンがほぼひとり語りですから、セリフはもちろんのこと、表情を作るのも大変。それをやってのけるには、「これは舞台だ」と言い聞かせることが必要だったんです。

──こんなにコロコロと登場人物とセットが全部変わるステージプレイなんて存在しないだけに、舞台だとするとめちゃくちゃ贅沢なものを作りましたよね。
ふたり:たしかにそうですね(笑)。
──この物語は完全にフィクションなんでしょうか? それとも実際に起きたことも一部入っていますか?
エスマイリ監督:事件自体はもちろんフィクションです。が、イランで実際に起きているさまざまな事象を取り入れています。
例えば、最初に遺体で発見された男の友人の妹・マーターのエピソード。マーターは戦争で母親を亡くし、違う町に行って15〜6歳の時に恋人ができます。それがすごく噂になって、父親や兄が彼女に対して怒り出します。この舞台になった町と地域は実際、女性の恋愛に関して非常に保守的なんですよ。ティーンエイジャーの女性が男性に恋したことを表現するだけで、家族からすごく責められ、最悪の場合は殺されたり自死したり…。マーターが焼死したというのも、現実に起きたことに着想を得ています。
──全シーンをほぼワンテイクでやっていますが、だいたいどれぐらいの回数、撮ったんでしょう?
ヘイダリ:平均はわかりませんが、とにかく何度も(笑)。さきほど、一度間違えたら最初からやり直しと申し上げましたが、やはりどこかでセリフを忘れちゃったり、うまく言葉が出てこなかったりしたんですよ。
私が暮らしている都会の物語ではないので、物語のエリアの人のように髪や髭を伸ばさないといけなかったり、慣れない環境の中だったこともあり、ミスは当たり前に起きますし、ライティングもいろいろ試しましたしね。監督が「それは違うんだよ」と言ってやり直したり、いくつか同じ感じで撮れても「もうちょっと恐れを出して」とか「もうちょっとイライラさを出して」とか「もうちょっとゆっくり喋って」とか。全く終わりが見えませんでした。
エスマイリ監督:ちょっとそれにつけ加えますね。バジェットの関係で、17日間で撮りきりました。短期間なので、全てを撮り切るためには、ひとりのキャラクターあたり半日で終えないといけませんでした。
また、彼が言った通りいくつかのパターンを撮りましたが、それは後で私が選ぶのが目的ではありませんでした。じつは、役者のみなさんによりリアルな芝居をしてもらうために、わざとテイクを重ねていたんです。これは、写真家としての長年の経験から生まれたものですが、テイクを重ねると役者の芝居から緊張感が生まれるんです。一度作った安心感を壊していたんですね。また、撮影時は音響も大きな困難でした。街の中で撮っているのに、車もバイクも何にも走ってないエリアのサウンドを作らないといけなかったことは、本作最大の難関でした。

ヘイダリ:それに、この撮影は真夏だったんですよ。
──え? 真冬の撮影とばかり…。
エスマイリ監督:真夏の8月に撮っているんです。暑いし、でも真冬の物語を撮っているから、役者はセーターやジャンパーなどの冬用の衣装を着ていて。
ヘイダリ:しかも、モノクロで撮るために、メイクは普段よりも何倍も濃くしないといけないんですよ。顔中すごくベタベタで、しかも暑いから汗でメイクは流れちゃう。役者全員、その辺はすごく苦労していました。
──低バジェット作とおっしゃいましたが、イランの映画製作の現状は?
エスマイリ監督:私が自分で作る映画は、イランの映画界では「アバンギャルド」ですよね。それはイコール、なかなか予算が集まってこないもの。一方、最近の若手の監督たちは、各国の映画祭の出品を目指して製作しており、映画祭のカラーに合わせて映画を作っています。そのため、外国の出資を探してきて映画祭向けの映画を作るのが、トレンドといっていいでしょう。
大きな映画祭には大体、こういうテーマが評価されやすい、といったイメージがあるんですよ。そうすると「じゃあ彼らが好む映画を作りましょう」となり、外国のプロデューサーを探してきて、比較的大きな予算がつく。そしてその映画が出品をされると、高く評価されるんです。自分は全くそういったアプローチをしないので、予算は0スタートでしたね…。東京国際映画祭は、この規模にしては非常に珍しいタイプの映画祭だと思います。なぜなら私の作品のようなアバンギャルド、アートハウス系の映画に注目してプログラミングしているから。本作で来日できたことで、昔ながらの映画祭が残っている、という安心感と喜びでいっぱいです。

インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)