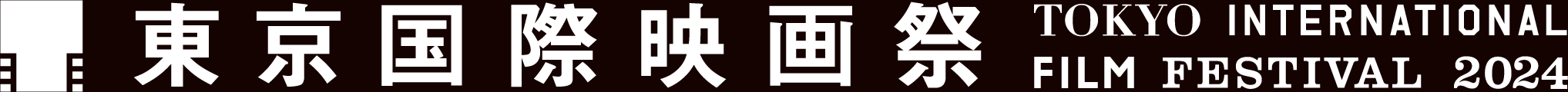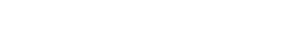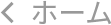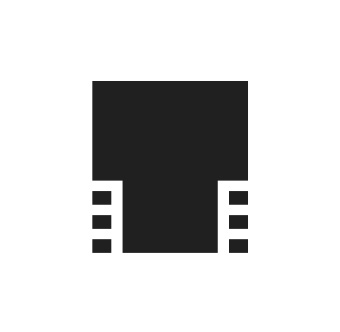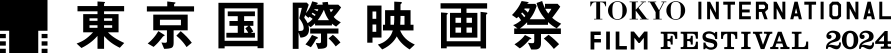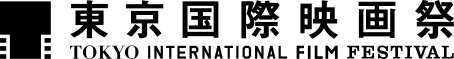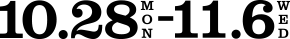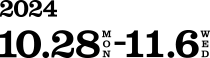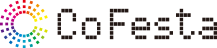10/31(木)コンペティション部門『敵』上映後に、吉田大八監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
司会:安田佑子アナウンサー(以下、安田アナ):それでは皆様、拍手でお迎えください。『敵』の吉田大八監督です。
吉田大八監督(以下、監督):こんにちは。監督をしました吉田大八です。今日は朝一番から、あまり朝にはふさわしくない映画を観に来ていただいて(会場笑い)、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
安田アナ:ありがとうございます。監督、ワールドプレミアですね。
監督:そうですね。世界で1番最初に観ていただいた観客の皆さんを前にしている僕です(会場笑い)。
安田アナ:どうでしょう。皆さんの顔を見て、敵に見えますか。
監督:まだわからないですね(笑)。
安田アナ:映画は、本当に「映画を観たな~!」という充実感や気持ちよさがありました。
監督:ありがとうございます。
安田アナ:全員が腕を見せ合った感じでした。
監督:そうですか。すごく嬉しい。ありがとうございます。
安田アナ:白黒映画なことに驚いた方もいらっしゃったと思います。あえて初の白黒に挑んだ理由を伺いたいです。
監督:正直に言うと、この映画を撮るにあたり、昔ながらの日本の家をどのように撮っていたのかということの参考のために、古い映画を色々と観たんですね。それに影響されて、打ち合わせの最初の方で、白黒にするのはどうかとなんとなく提案したんですよ。
白黒映画っていうと観る人が少しハードルを感じてしまうので、普通はプロデューサーが止めますが、今回のプロデューサーは勇気があって、いいんじゃないかと言ってくれて。すぐにOKが出たので、そのまま白黒になったというのが経緯です。
皆さんも、映画をご覧になっておそらく感じられたと思いますが、映画が始まって2・3分で、今自分が観ている映像が白黒かカラーかは多分問題じゃなくなるんですよね。逆に、日常で見る景色に比べて要素を制限している分、映画に対する没入感がより強くなって、観ている人の想像力も働くし、結果として映画にはすごくプラスになったと僕は思ってますし、皆さんもそうだったらいいなと思います(会場拍手)。
安田アナ:この作品は1998年の筒井康隆さんの小説が原作ですよね。 なぜ、今回この作品を取り上げようと思ったのですか。
監督:きっかけは、コロナウイルスの影響で、本屋さんも閉まってあまり外に出かけられない時に、家にある古い本を片っ端から読み返した中にこの本があったことでした。出版された当初に一度読んでいたのですが、ふと手に取って読み返すと、若い時に読んだ印象と全然変わっていて。自分が年を取ったせいもあるし、あとは、当時、コロナ禍の状況でみんなが儀助(主人公の渡辺儀助)みたいな生活を強いられていた。色々な意味で切実なものを感じて。そのことについて考えているなかで、何か映画を撮ろうと声をかけてくれた人と色々と話しているうちに、「その題材いいんじゃない」と話が割と簡単にまとまったんですよね。そうして脚本を書き始めたのがきっかけでした。
──Q:この物語の中には主題の一つとして認知というものが通底していますが、その点についてどのように投影していったのかお聞きしたいです。
監督:僕は、この映画を制作し始めて、 途中からこの主人公は認知症じゃないかと確信を強めていて。どういうことかというと、 彼はある程度、もしかしたら無意識が大きいかもしませんが、ほぼ無意識に自分から夢や妄想の世界に自ら進んで身を投じているという。そういうイメージでこの映画の撮影やその後の制作自体を続けていったのです。本当の認知症っていうのを僕も自分事としてわかってるわけではもちろんないですが、結局どこまでが理性でどこからが理性じゃないかっていう線引きが、自分自身にも客観的にもできなくなる状態だと思っていて。主人公の儀助は、自分の理性を持ってこの世界に踏みとどまろうとした人。だけど、昔好きだった人に会いたい、昔経験した楽しい出来事をもう1回経験したいと思い、自分の無意識が暴走して、自分を夢や妄想の世界に引っ張り込んで振り回すことを許していく、という解釈でこの映画をつくりました。
安田アナ:原作の筒井康隆さんが、「これは映像化できないと思っていた」とインタビューで答えていらっしゃいました。 本だと、何か引っかかった時にもその都度読み返しことができますが、映像は流れていきます。そうした点での、つくりかたの工夫をお聞きしたいです。
監督:現実から非現実にジャンプしたり、いつの間にか戻ってきたりするような展開のことを仰っているのだと思います。僕は10代の頃から筒井先生の愛読者で、自分の体の7割ぐらいが筒井さんでできている感覚でいるのです。自分のセンスは筒井さんのセンスと同じだと言うと怒られるかもしれないですが、勝手にそう思っているので、扱いが難しいと思ったことは正直ないんです。もし観ていて、そうした展開を自然に感じてくださったのだとしたらそういうことかもしれません。
映画を撮っていて、すごくリアルに撮ったつもりなのにシュールだと言われて、自分ではピンと来ないことがあるんです多分が、そういうことですね。基準が違うんだと思います。
──Q:この映画では、ゆっくりと過ぎていく季節の中で、淡々と儀助が生活をしていきますが、 白黒映画であることによって、そうした儀助の姿をフラットに感じられた気がしました。そうした姿と対比して、抑えられてきた感情を爆発させるということを演出上で意図してきたものなのでしょうか。
監督:先ほどの質問にもありましたが、最初に白黒を選んだ理由の1つに、特に前半のストイックな老人の生活を描くとき、モノクロのトーンが感覚的に合うんじゃないかなと思ったのが最初の理由でした。皆さんの中で、モノクロームで彼の生活を観続けているうちに、モノクロであるがゆえに観ている人の想像力の感度がどんどん高くなるというか、もちろん起きる出来事は変わるけど、前半も後半もペース自体は変わりません。そうしなかで観ている人にそう感じてもらえているということは、モノクロの大きな効果だったのかなと思っています。
安田アナ:俳優さんたちの力もすごかったですね。この人じゃなきゃ演じられないという人たちがキャスティングされていた気がしますが、まずは長塚さん。そのままでした。どうして長塚さんにお願いしたいと思ったのですか。
監督:昔から本当にファンだったのですが。やっぱり、引退した老大学教師ってある種、知性を感じさせつつ、でもやっぱり枯れきっていないという、人間として、男性としての色気を残しているものですよね。その絶妙なバランスを表現してくれる俳優さんをイメージした時に、長塚さん以外思いつかなかったんですよね。長塚さんにイチかバチか脚本を読んでもらって、こんなのできないと思われるか、すごく面白いと評価してもらえるかの2つに1つだと思いました。長塚さんと共にあった企画だという風に思っています。
安田アナ:教え子を演じた瀧内公美さんも。どうして瀧内さんに?
監督:これまでの彼女のお仕事を拝見していて、この役にうまくマッチすると思ったのが理由です。彼女は、自分でも言っていましたが、モノクロ映えするんですよ。現場でモニターを観ていても、昔の女優さんがいるのかなという感じで。息を飲むぐらいの衝撃でした。もちろんカラーでも彼女は素晴らしいお仕事をされていますが、モノクロの瀧内さんを発見できたことは、この映画の手柄の1つなんじゃないかなと勝手に思っています。
安田アナ:そしてスナックで出会ってしまう、今、日本映画、ドラマで引っ張りだこの河合優実さん。彼女は短い場面ながら印象的でしたね。
監督:すごく色々な意味で、打てば響くというか、この役ははっきりしないじゃないですか。彼女が実は何者で、どういう意図を持って儀助と仲良くしていたかっていうことを映画の中でも説明しなかったし、河合さんにも説明しなかったのですが、彼女の勘の良さで、監督がそれぐらいのバランスで伝えたいんだろうなっていうことを、脚本を読んで正確に理解してくれていました。彼女と最初に会った時に「この企画って監督がやりたかったんですか」って言われまして「そうですよ」って答えたら、「そうだと思いました」と。「これ、誰かがすごくやりたいなと思ってそうな企画だから参加したいと思いました」って言われたんですよ。ぐっとくるじゃないですか。 もうその時からファンになっちゃいました。