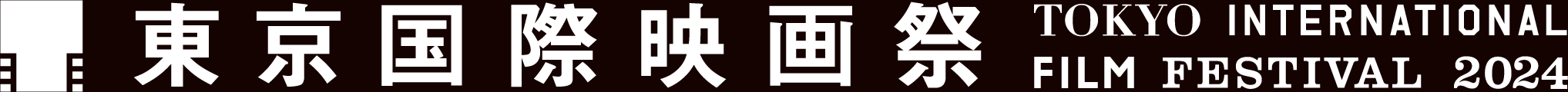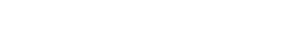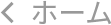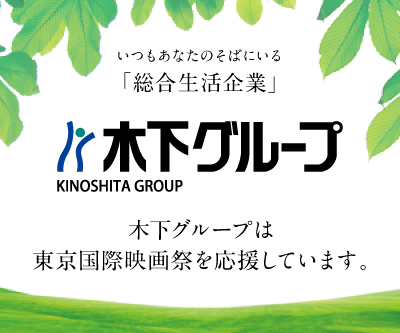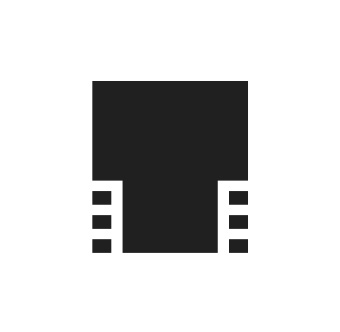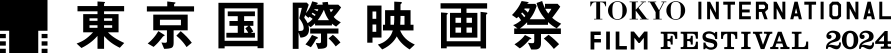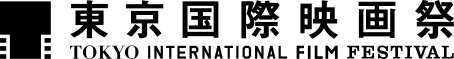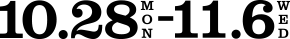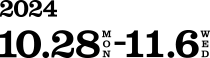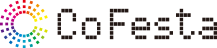モハッマド・エスマイリ監督(右)、モハマドマフディ・ヘイダリさん(左)
11/1(金)アジアの未来『冷たい風』上映後、モハッマド・エスマイリ監督(監督/脚本)、モハマドマフディ・ヘイダリさん(俳優)をお迎えし、Q&Aが行われました。司会は阿部久瑠美 鎌倉市川喜多映画記念館 学芸員(以下、阿部さん)です。
モハッマド・エスマイリ監督(以下、監督):皆さん、こんばんは。ワールド・プレミアを日本でご覧いただけて、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。 少し複雑な映画だと感じられたと思いますが、楽しんでいただけていたら嬉しいです。
モハマドマフディ・ヘイダリさん(以下、ヘイダリさん):皆さん、こんばんは。自分の作品を初めて観たこと、日本の皆さんと一緒に観られたことをとても嬉しく思います。ありがとうございます。劇中で赤十字と呼ばれる場所から退院し、私が演じた役が証言をする場面があります。その証言を受けて、劇中の登場人物がアクションを起こしますよね。そのことから、自分の役が少し分かっていただけると思います。
阿部さん:実は、お二人は、日本へ、東京国際映画祭へゲストとして来ていただけるかどうかがギリギリまで分かりませんでした。 中東情勢が日々変化する中で、飛行機が飛ぶかわからなかったなか、今日こうして無事にお披露目の舞台に立っていただくことができました。本当にようこそお越しくださいました。ここに来るまでの道中、何か大変なことはありましたか。
監督:東京国際映画祭への出品が決まった時期に、私たちの住むイランでは様々な事件が起き、とても混乱していました。日本の皆さんは、ニュースなどで中近東の様子をご覧になり、ある程度のことはご存じかと思います。我々は、大変な状況の中で生活し、映画を作り、また、何かが起きやしないかと毎日のように心配しながら、なんとか生活を送っています。 戦争が起きたり、制裁があったりと大変な状況ですが、いつかこの世から戦争が完全に消えて欲しいと、そればかりを願って生活しています。
ヘイダリさん:実のところ、一度は日本に来たいと思っており、数か月後に(日本へ行く)予定を立てていたのです。そうしたなかで、東京国際映画祭への出品が決定し、映画とともに日本へ来ることができ、とても嬉しいです。しかし、出発の数週間前から様々な事件が起きて混乱状況が続き、そのうえ飛行機もほとんど飛ばないという状況になり、日本に来られるかどうか、本当に分かりませんでした。結局、3日間ほど違う国に滞在しながら、3つの飛行機を乗り継ぎ、やっとのことで日本に来たのです。ここに来られたことをとても嬉しく思いますが、イランがこうした大変な状況にあるということを皆さんにも知ってほしいです。
阿部さん:ありがとうございます。お話をお伺いできることが本当に貴重な機会だと思います。
──Q:カメラ位置が主観視点になっていますが、人の顔の高さとは思えない位置にある場面もあります。カメラの高さはどのような基準で決められたのですか。
監督:撮影のテクニックとしては、撮影前には、全ての場面をまずは1つのレンズ(カメラ)だけで撮ろうと計画していて、アングルについても同様に、どの角度から撮るか計画し、そのプランを最初から最後まで守って撮影しようと考えていました。いざ撮ってみると、場合によっては難しい部分もありましたが、私は今まで自分の考え方を信じて貫こうと頑張ってきたので、今回もなるべくそうしようと試みました。
私は、映画か写真かを問わず、個人的にローアングルがとても好きなので、この映画もそのように撮ろうと考えていました。なぜローアングルを選ぶかというと、キャラクターがさらに大きく見え、より感情的に見えるからです。撮影のはじめにそう考えて撮ろうと思っていました。
──Q:外から差し込む光がすごく印象的でしたが、自然光なのか、照明の光なのかをお聞きしたいです。
監督: 自然光ではありません。インディペンデント映画(自主制作映画)は予算がタイトなので、撮影費用をできるだけ抑え、短い期間で撮る必要があります。そのため、スタジオでのライティングが多いんです。
撮影監督にはお礼を申し上げないといけませんが、自然光に近い照明を彼がデザインし、つくってくれました。インディペンデントでは、やはり、予算とタイミングの調整が一番大変です。早く仕上げる必要がありました。
──Q:英語タイトル『The Bora』はどのように選びましたか。
監督:その質問に答える前に、この脚本を一緒に書いた作家のペイマン・エスマイリさんの話をします。親戚ではないのですが(笑)同じ名前で、多くの本や小説を書いており、その中の一冊に『”Bora”(冷たい風)』という話がありました。そこで、この作品のタイトルを選ぶときにも、話の中の『”Bora”(冷たい風)』が当てはまるので、タイトルとして選ぼうと思ったんです。
“Bora”というのは、冷たい風のことなのですが、その冷たい風がいつ吹くかというと、これから冬が始まるタイミングなんです。その話の中では、この冷たい風が吹くと、色々なキャラクターが良くない状態に陥ったり、殺されてしまったりします。そうした意味では、まるで1人1人のキャラクターに冬が始まったかのようでした。
また、映画の中でも説明がありましたが、”Bora”というのは、冷たい風が人を救うというような意味でもありましたが、もう1つには、冷たい風に当たりながら生きて帰ることができると、その罪が赦されたという意味でもあります。こうした2つの意味を持っているという意味でも、この作品に合うタイトルは『”Bora”(冷たい風)』だと思って選んだんです。
──Q:再度、主観的なショットについてお伺いしたいです。なぜ映画を撮る手法として主観的な表現方法を選ばれたのでしょう。
監督:これは説明が少し長くなりますが、3つのことを説明しなければいけません。1つには、先ほどお話しした、 ペイマン・エスマイリさんの小説を読んだ時に、話の中に11の手紙のようなものが登場してそこで物語が進んでいくのです。
そして、もう1つは、コロナの時期は、なかなか外に出られず、映画館に行かなかった時には、ポッドキャストをよく 聞いていたんです。今まで読んだことのない物語も、オーディオブックなどで聞いていて、そうしていると、自分が色々な物語の中に入ったかのような感覚になりました。
そして最後の1つは、アッバス・キアロスタミ監督の『クローズ・アップ』を観たことでした。キアロスタミ監督の映画の中では、私たちは起きている出来事自体を見ることはできません。それは、登場人物が語ることの中で、今起きていることを観客に分からせるためでした。これと同じことを自分の作品でも出来たらと、色々考えたんです。
劇中では、観客は、刑事の顔は見られないんですね。1人の刑事が色々な人の証言を聞いている様子を映しているので。なぜこのようにしたかというと、(映画を)観ている人たちが、その刑事の代わりに色々な人の証言を聞けばいいんだと思ったからです。 要するに、皆さんは、今映画を観ながら、その刑事の役になって話を聞いていたということなんです。そうした作品にするために、フレームは色々と変わってしまうんですが、 自分の中で主観ショットで撮るということを守ろうと決めて、こうした作品をつくりました。