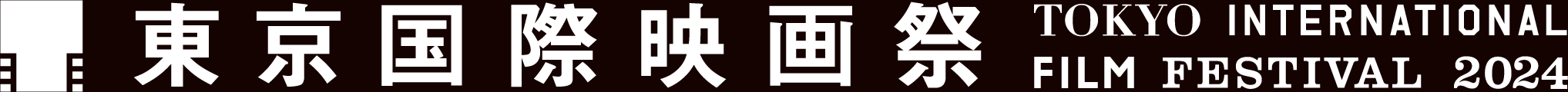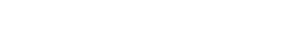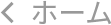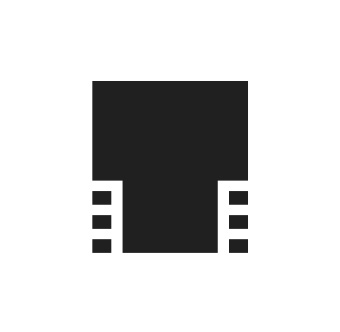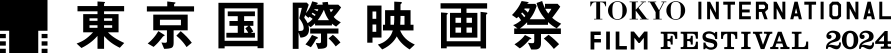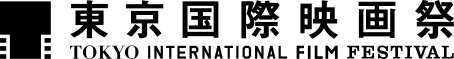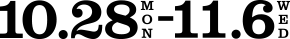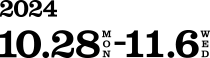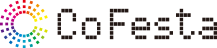10/31(木)コンペティション部門『アディオス・アミーゴ』上映後に、イバン・D・ガオナさん(監督/脚本・左)、モニカ・フアニタ・エルナンデス・ドゥキーノさん(プロデューサー・右)、ウィリンㇳン・ゴルディジョ・ドゥアルテさん(俳優・右から2番目)、ヨハニニ・スアレスさん(俳優・左から2番目)をお迎えし、Q&Aが行われました。
イバン・D・ガオナ監督(以下、監督):こんばんは。今日はこの上映にお越しいただきありがとうございます。この機会を皆様とともにできることを、非常に嬉しく思います。市山さんにも感謝したいと思います。市山さんとは、今年、コロンビアのカルタヘナでお会いしました。また、ここにいらっしゃる観客の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。
私たちはコロンビア生まれで、チカモチャ渓谷というアンデスの山間で育ちました。皆様とお話できるのを非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。
ウィリントン・ゴルディジョ・ドゥアルテさん:こんばんは。まずはこの劇場にお集まりいただいた観客の皆さん、映画祭のスタッフの皆さん、審査員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。この舞台に、監督のイバンさんやプロデューサーのモニカさん、俳優のヨハニニさんと一緒に上がることができて、この夜は非常に美しい瞬間だなと感じています。この映画を観てくださった皆さんが、少しでも気に入っていただけると、とても嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。
ヨハニニ・スアレスさん:こんばんは。今日はお越しいただきありがとうございます。非常に嬉しく、光栄に思っております。東京国際映画祭のディレクターの市山さんやスタッフの皆さんにも、感謝を申し上げたいと思います。
この作品の制作は非常に大変で、努力が必要な映画でしたが、 その分、熱意を込めて世界中のみなさんに届くように作ったつもりです。この会場にいらっしゃる日本の皆さんは、コロンビアから遠く離れたところにおられますが、何か、この映画を面白いと思っていただけたら、とても嬉しいです。距離は非常に離れていますが、1人の人間として、互いを尊重したり愛したりすることができると思っています。ありがとうございます。
モニカ・フアニタ・エルナンデス・ドゥキーノさん(以下、モニカさん):こんばんは。この作品を非常に誇りに思っており、皆さんと少しの間お話できるのを非常に楽しみにしております。市山さんはじめ、映画祭のスタッフの皆さん、ここにいらっしゃる観客の皆さん、 客席にいらっしゃるスタッフの方、コロンビアにいる100人ほどのスタッフの方に感謝を申し上げたいと思います。映画を気に入っていただけたらとても嬉しいです。少しの間ですが、お話できたらとても嬉しいです。ありがとうございます。
司会:市山尚三プログラミング・ディレクター:さきほど監督からも話がありましたが、今年、カルタヘナ映画祭というコロンビアの映画祭に招待され、その時にまだ完成する前の段階のものを観させていただき、本当にびっくりして、ものすごく楽しんで観ましたので、今回招待することにさせていただきました。コロンビアに行くまでには乗り換えもあり、24時間以上の時間がかかります。帰りもそうなのですが、とても長い道のりでした。この長い道のりをわざわざ来ていただき、本当にありがとうございますと、まずお伝えしたいと思います。
監督:ありがとうございます。
──Q :コロンビアではこうした歴史劇というか、時代劇というものが、よく制作されるのでしょうか?また、とても幻想的なモチーフがエンターテインメントとして入る映画でしたが、どのようなインスピレーションがあったのかお伺いしたいです。
監督:コロンビアでは、映画に関する法律ができた影響もあり、この20年間で以前にも増して映画がたくさん作られるようになりました。この20年というのは、私たちと共にあった20年というのか、法律ができてからの20年を私たちはこのチームで生きてきたわけで、そうした状況下で、私たちは映画を作り歴史を書き換えていくということを意識するようになりました。映画だけではなく、文学や演劇でも、歴史を扱った作品が増えていると思います。
その歴史を語り直すという作業のなかでは、主要で公的な歴史というのは、常に特権的な権力を持つ立場の人が書いてきたり、語ったりしてきたわけです。そうすると、そこで語られないのは、民衆であったり、先住民であったり、女性であったり、そうした人たちの歴史はなかなか語られてきませんでした。
そこで、私たちは、映画のフィクションという力を使って、例えば、そうした語られてこなかった先住民の物語やコロンビアにいる黒人とされるアフロ系の人たちの話を書きたいと思ったんです。そこで、 戦争の歴史がどのように人に影響を与えるかということ、家族を断絶させたり、信仰に影響を与えたりという、そういう過程をフィクションという面からアプローチをしようと思ったという次第です。
──Q :私は外国から来た者で、映画を観て、非常にショックを受けました。ショックというのは、映画の全体に、敗者の感覚、負けるということへのフィーリングが感じられたことに対してです。監督は、そうした感覚をどのように感じておられたのでしょうか?その負けた者たちをどう受け入れるか、そして、私たち自身をどう許すことができるのか、そうした大きなテーマを感じることができたので、この点についてお話をお聞かせください。
モニカさん:お答えするのが非常に難しい質問だと思います。その点については、映画を作っているときに議論した点でもありました。政治的局面が非常に難しい時であったので、そのような議論があったということです。
歴史的状況というのは、周回するというか、繰り返されるものだと思います。戦争が起こっては終わり、また起こっては終わるということが常に繰り返されるのだと思います。
そういう世界、つまり、歴史が繰り返される、戦争が繰り返されるという世界において、映画をはじめとする芸術というものは、その時のその感情を和らげたり、痛みを取り除いたりするものであると思います。また、ひとつの逃げるための口実というか、逃げ込める場所、隠れ家のようなものでもないかとも思っています。
私たちは、この社会に生きる1人の構成員として、社会の構成員として、ポジティブというかアクティブな姿勢を常に取っていきたいと思っています。人を許すことによって、人は前に進んでいけるのではないでしょうか。
監督:最後に、コロンビアという国は、強烈な歴史を生きてきて、例えば、ある時期では左派のゲリラが非常に暴力を振るった時期もありましたし、右派の民兵組織が幅を利かした時期もありました。また、公的な職に就いている人が、誰かを優遇して、誰かをそうしないとか、そうした不平等なことがまかり通っている社会です。
そうした左派だったり右派だったり、政治的ポジションが異なる人が日常を共に暮らしている、その中で憎しみ合ったり愛し合ったりするのがコロンビアの社会なのですが、そうした政治的な違いがあっても人は一緒に生きていかなければならず、それ自体はそれほど大変ではなく、ただそこで生きているということなのだと思っています。
今、コロンビアは歴史を初めて左派の政権が握っている状況です。200年ほど前までは植民者のスペイン人たちがすべてを掌握していました。例えば、今は左派の政権の元で私たちは暮らしていますが、そうすると立場の違う右派の人とも出会い、共に暮らしていくわけですよね。そうした、政治的ポジションが違う人たちと日常で普通に出会う状況があります。ただ、政治的思想、イデオロギーは違っても、先ほど言ったように、愛し合ったり、憎しみ合ったり、友達になったりすることがあります。この映画ではそういう状況、対立する2つの思想を持った人たちが出会ってしまう、直面してしまうという状況を描いており、そうしたところで友情が生まれるとしたら、それは何に基づいて生まれるのか、どのようにして友情というものが成り立つのかということが1つのテーマでした。