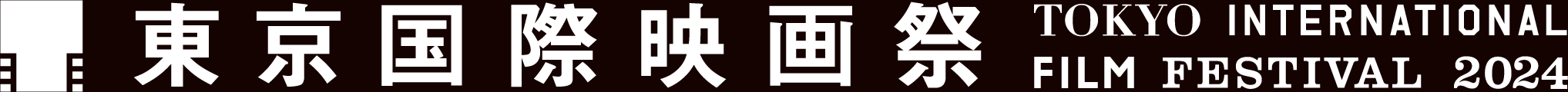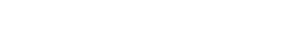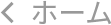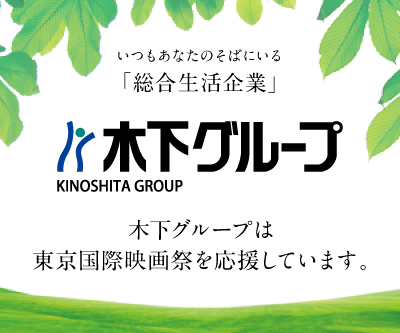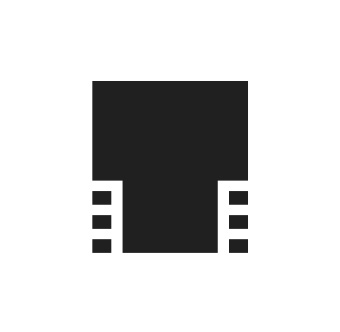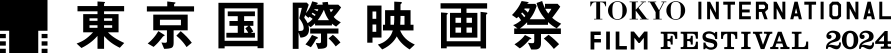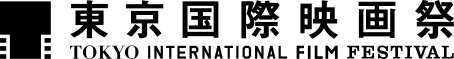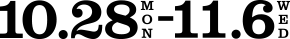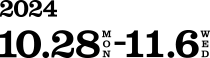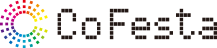リウ・ジュエン監督(右)、ジャオ・ジンさん(プロデューサー・左)
11/2(土)ワールド・フォーカス『怒りの河』上映後、リウ・ジュエン監督(監督/脚本)、ジャオ・ジンさん(プロデューサー)をお迎えし、Q&Aが行われました。司会は、映画ライター・コラムニストの新谷里映さん(以下:新谷さん)です。
リウ・ジュエン監督(以下、監督):皆さん、おはようございます。今日はお天気がこんな具合でたいへんな雨の中、来てくださって本当にありがとうございます。
ジャオ・ジン(以下、ジンさん):おはようございます。私はこの作品のプロデューサーのジャオです。どうぞよろしくお願いします。お目にかかれて嬉しいです。
新谷さん:この題材は、長い間温めてきたものなのか、突き動かされる何かがあったのか、作品を作るきっかけを教えてください。
監督:7年前のことですが、実は雲南省の方で生活していたときがありました。その間に、この映画に登場するジー・ホンのような女の子、父親のフーさんのような男性と出会いました。その時、彼らに起こった様々な物語を知る機会がありました。
当時、私はその地域の学校で教師をしていましたが、そこで出会った色々なことが私の創作意欲を駆り立てました。
新谷さん:国境の川にかかっているロープは、実在するものでしょうか?
監督:7年前とか10年前の私が知る範囲では、実際にこの川を渡るために使われていた交通手段の1つでした。今はもう、観光用になってしまいましたが、実在しています。
しかし、雲南省では、ロープはとても実用的な道具として、(川を)渡るためなどいろいろなことに使われています。
新谷さん:ジンさんは、監督から作品のアイデアを聞いたとき、どんなお気持ちでしたか。
ジンさん:監督からこの企画を聞いたのは、2020年の秋でした。私は、監督が書いた脚本を読んだとき、本当に驚きました。非常に素晴らしい脚本だと思ったので。
監督は、非常に取材力のある方で、ご自分で様々なフィールドワークをして、しっかりと取材をされていることがわかりました。この点が、リウ監督と他の監督の違うところです。リウ監督は、ドキュメンタリー作品もたくさん撮っていらっしゃるので、実際に、生活の中で人間がどういう風に生きているか、どういうものを撮ったら共感が得られるのかということをよく分かっていらっしゃいます。その土地に密着した、その土地で生きている人たち特有のものをすべて脚本に書き込んでいらっしゃいました。そのため、私にとても感動を与えましたし、作品としても、重量級の、非常に素晴らしい作品になると確信しました。
──Q:仏像など、仏教に関連のあるものがたくさん登場しますが、なにか意図を持って物語を描いたのですか。
監督:撮影した土地の生活に実際にあるものを撮影しました。やはり、数百年の間、その土地に生き続けてきた人たちが、生活の中に溶け込んだ(仏教関連の)ものを、今も持ち続けているということ。仏教が非常に重要な特徴になっていて、仏教精神が彼らの生活の中で、大事なよりどころとして扱われています。
現地の人は、家庭で、仏教に対しても、他のものに対しても、多種多様な価値観を持って今を生きているように感じました。仏教の大きな教えである「善と悪」についても、どのように仏教を受け入れるかは、個々人の考え方(を支える)の一部分となっています。ですので、人によって、仏教に対する思いや考え方に大きな差があることは確かです。ですので、そういう風に、この映画では描いています。
──Q:劇中に登場する、屠牛(とぎゅう:食用のために、牛を殺すこと)はどのような考え方をお持ちで、このように映画の中に組み入れていったのでしょうか。特に、屠牛の方法を、女の子に伝承をするという点について、詳しくお聞きしたいと思います。
監督:屠牛は、冒頭と最後の方のシーンに出てきますが、それなりの意図をもって(屠牛のシーンを)登場させました。
この行事は、現地に今も残る非常に重要なイベントの1つで、現地の人にとって、その祭りは、精神的なよりどころになっています。
それをこの2人の人物に託して、屠牛に込められた土地の人々の思いを表現したかったんです。物語の中で伝えたかった「命に対する人生とは」「命とは」ということへの理解を2人に託しました。
(監督が出会った)父親の男性は、屠牛をすることは、自分を見つめることだ、と語っていました。彼にとって、祭りの中で牛を殺して祀ることは、彼の人生を物語っていると思います。また、彼の職業自体、職業に対する態度を、そこで語っているわけです。そうした意味で、父親にとって、(屠牛は)自分をどう見つめるかという意味合いを持ちます。その意味で、あのような表現になりました。
(プロデューサーの)ジンさんに、ミャンマーと中国の国境辺りでの映画制作の困難をお話しいただきたいです。
ジンさん:国境での映画制作がどれだけ大変で困難だったかをお聞きになりたいということですよね。
ミャンマーのシーンは、現地で撮影することがとても難しかったので、ほとんど中国国内で撮りました。美術、脚本、撮影についても、監督のこれまでの様々なドキュメンタリーや、(監督が)現地で生活した経験があったので、(ミャンマーのシーンの)撮影場所も中国国内で見つけることができました。
監督:雲南省の中の小さな町を描くにしても、民族についても同じです。建築物も、非常に独特な建築がかなり多いものですから、様々な小さな町を選び、コラージュして撮っていくことを心がけました。
新谷さん:撮影期間はどのくらいだったんですか。
監督:全部で60日かけたんですが、実際の撮影は55日で、残りの5日は風景だけを撮ったり、そういった補足撮影というように使いました。
──Q:ラストシーンにはどういう意図があるんでしょうか。
監督:特に、これで続編を撮ろうなど、そうした意図があったわけではなく、観てくださった皆さんに、自由に解釈していただきたいと思って、撮影しました。
ジンさん:日本ではどうかわかりませんが、中国国内でこの作品が受け入れられて、続編を作れるということになれば、ラストシ-ンから繋がるところで続編が始まるかもしれません。
新谷さん:最後に、一言ずつメッセージをいただけますでしょうか。
監督:今日映画を観ていただいて、この作品を気に入っていただけた方は、友人などにぜひ推薦していただければと思います。より多くの方にこの映画を観ていただきたいです。今日はこの作品の上映にお越しいただき、本当にありがとうございました。
ジンさん:私は東京に来たばかりなんですが、これまで記者としても、作家としても、様々な映画祭に参加していますが、東京国際映画祭のお客様はとても誠実で、真面目に観てくださった方が多い気がしました。
中国からいらっしゃったお客様もいらっしゃいますよね。そうした観客の皆さんにお会いできて、本当に嬉しく思います。またぜひ映画を観に来てください。