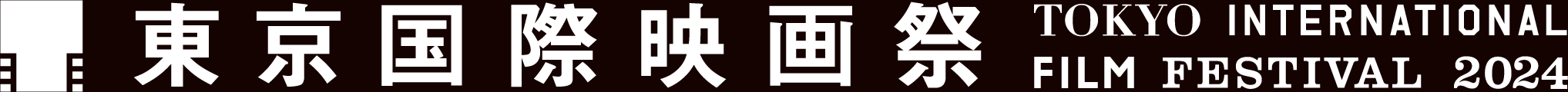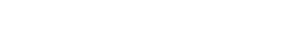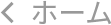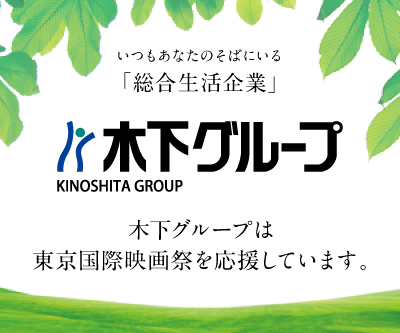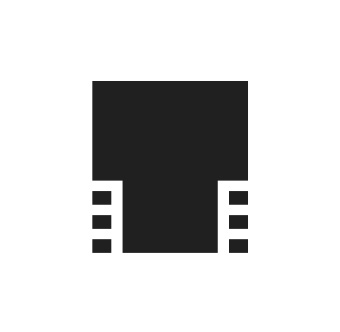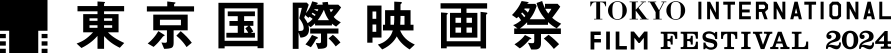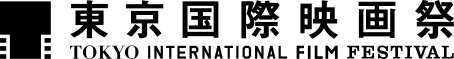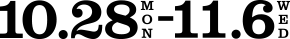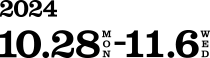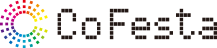エミネ・ユルドゥルム監督(中央)、エズギ・チェリキさん(右)、バルシュ・ギョネネンさん(左)
11/2(土)アジアの未来『昼のアポロン、夜のアテネ』上映後、エミネ・ユルドゥルム監督(監督/脚本)、エズギ・チェリキさん(俳優)、バルシュ・ギョネネンさん(俳優)をお迎えし、Q&Aが行われました。司会は、高崎郁子さん(以下:高崎さん)です。
──Q:風や月、太陽が本当に素晴らしかったのですが、映し出される天気の意図や、どのような工夫をされたのか、監督にお伺いしたいです。
また、俳優のお2人は、日が差す短時間で集中して撮る必要があったかと思います。何を意識されたのか、監督からどのような指示があったのか、お伺いしたいです。
エミネ・ユルドゥルム監督(以下、監督):作品の舞台となるシデ(トルコの南地中海沿岸にある都市)はとても特別な場所で、色、空、そして様々な光にあふれている世界でも特別な、自由な場所として有名です。私たちが撮影を行う上で、これらの要素は撮影に好都合でした。インパクトがあり、作品に良い影響を与えると思ったからです。ただ、日中と夜の温度差が激しく、例えば、昼は海に入れるほどの暖かさでも夜は非常に寒くなる、といった点には注意する必要がありました。
高崎さん:シデという重要な場所で映画を撮る、ということは監督が決定されたと思います。これまで、脚本家やプロデューサーとして映画に関わってこられたと思いますが、やはり、シデという場所ありきでこの物語を作り、監督したということでしょうか?
監督:はい、そうです。トルコと言っても、舞台はアナトリアという台地です。地理的観点、歴史的観点からみても、トルコはとても古い国です。長い歴史の中に様々なヘテロドックス的な(オーソドックスではない)多様な文化を持っており、時間軸が異なる分、深く長い歴史があります。
それらすべての歴史をアナトリアという土地は持っています。私はそうしたことから、映画の製作を考え始めました。トルコは、乾いた草地の単なる大地ではありません。非常に長い人類の歴史があり、それに深い影響を受けてきたこのシデという場所で撮影をすることが大事でした。
──Q:ローマ時代の女性神官の神殿が信仰を強制したという7月の神についてのお話を伺いたいです。
監督:ローマ時代と仰いましたが、これはローマ時代よりもはるか昔のことです。 アナトリアナ文化の歴史はとても古く、ルウィ語が用いられていた古い文明の時代に女性神官は存在していたのです。この文明はヒッタイト帝国と同じ時代に存在し、残念なことに、彼女たちはヒッタイトの奴隷になってしまいます。この歴史を強調したいと考え、ローマ時代よりもずっと前のできごとですが、さらに遡ってみようと思いました。
ここでつけ加えると、この7月の神という信仰はアナトリアではかなり流行しました。さらに前の時代には、アナトリアの地母神、キュベレー神の母型中心社会が成立していました。現代社会は、男性中心社会、家父長的社会が中心ですが、時代を辿るとそうではなかったんですよ。
今、(男性の)バルシュさんにはこの件のお話は聞かないでおきますね(笑)
バルシュ・ギョネネンさん(以下、ギョネネンさん):(笑)
高崎さん:ヒュセイン役を演じたバルシュさんは、演じるにあたって何に気を付けましたか。
ギョネネンさん:特殊な設定の役柄ですが、特別であることを演じるのではなく、普段役を演じる時と同じように演じました。
難しかったことは、物や人に触れないという設定です。何かオブジェがあってもそれには触れない。例えば、芝生があっても触ってはいけない、などです。これは技術的な面で難しいことでした。そのほかにも、役者間のコミュニケーションの面では通常お互い触れ合うことがあります。今回、この触れないという制約が私たちにとって困難の1つではありましたが、エズギさんは役柄を演じる上で大変素晴らしいパートナーでしたし、素晴らしい作品になりました。
──Q:タイトル『昼のアポロン、夜のアテネ』についてもお伺いしたいです。「昼のアポロン」は、母親のイメージで繋がっていて、「夜のアテネ」は、死者の世界を指していると思いましたが、この理解であっているのでしょうか。
監督:お望みのように解釈していただければそれでいいと思います。
──Q:音楽がとても素敵でしたが、今後、音楽アルバムのリリースはありますか?
監督:音楽アルバムについては、この映画に配給がついた時点で作成しようと考えております。確かに素晴らしい音楽ですので、作曲家についてもご紹介します。バルシュ・ディリさんという作曲家で、私たちの前作の映画でも作曲を担当しています。残念ながら今回は来日できませんでしたが、このようなコメントがあったことを彼に伝えます。ありがとうございました。
──Q:ストーリーを作るにあたって、何から発想を得られたのでしょうか?
監督:日本の映画から大きな影響を受けました。小津安二郎監督は私にとって、大変影響を受けた、素晴らしい監督です。
このストーリーにご関心があるということですが、トルコでは文化・芸術的な映画を作る時、どんなに文化的に展開をしている映画であっても、角がある、悲観的なストーリから始まります。また、キャスティングにおいても、男性の俳優が中心で、女性たちは同じように俳優として活躍できないという背景があります。この状況に抵抗したい、反抗したいと思い、このストーリーを練り上げました。これまでとは違う、トルコにはなかった映画を作りたい。コミカルでありながら感動的で、ホッとした感情を与える、そんな映画であってほしい。そして、鑑賞される方が良い感情を持っていただけるようにと狙い、考えました。そのため、生半可な気持ちで作ることはできません。私たちは、俳優の皆さん、アーティストの皆さんと一丸となって頑張りました。
今、世界はとても困難な状況にあり、不幸なことがたくさん起きていますが、私たちは希望にすがらざるを得ない時があります。希望をもたらすために、愛情や連帯、慈愛心を感じていただきたいです。映画を観終わったとき、誰1人として孤独感を感じない、そのような気持ちになっていただけたら、この作品は私にとって成功したと言えるでしょう。