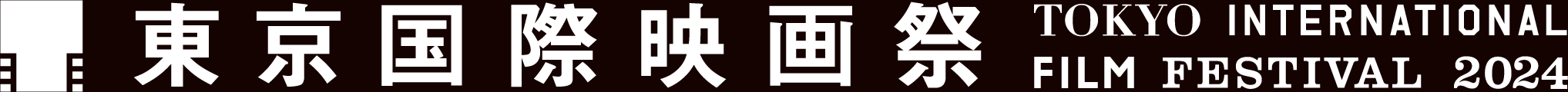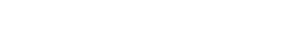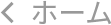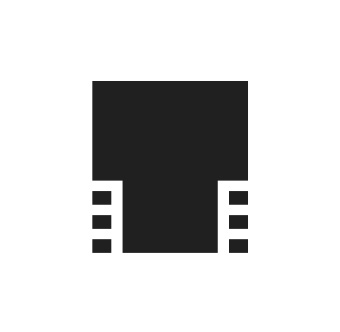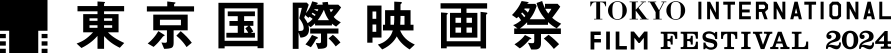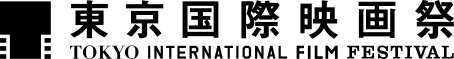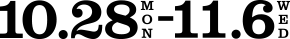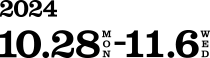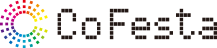東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月2日
コンペティション
『小さな私』
ヤン・リーナー(監督・左)、イン・ルー(プロデューサー・右から2番目)、ヨウ・シャオイン(脚本・右)、イー・ヤンチェンシー(チュンフー役・右から3番目)、ダイアナ・リン(チェン・スーフェン役・中央)、ジャン・チンチン(チェン・ルー役・左から3番目)、ジョウ・ユートン(ヤーヤー役・左から2番目)

チュンフー(イー・ヤンチェンシー)は脳性麻痺に生まれついたが、人並みに働いて、自尊心を持って生活したいと願っている。ある日、彼は祖母のチェン・スーフェン(ダイアナ・リン)が所属するシニア合唱団の鼓手を務めることになり、公園で練習している最中、若い娘のヤーヤー(ジョウ・ユートン)と知り合う。
1999年、初めて撮ったドキュメンタリー作『老人』が山形国際ドキュメンタリー映画祭でアジア千波万波奨励賞を受賞。『春夢/Longing for the Rain』(13)、『春潮』(20)、『春歌(媽媽!)』(20)の「女性3部作」を撮り終えたヤン・リーナー監督の最新作。
障害を抱える若者を大学受験や母との葛藤、働く喜びといった等身大の目線で描いた一作で、笑いあり涙ありの脚本を書いたのは、『妻の愛、娘の時』(17)のヨウ・シャオイン。『フェアウェル』(19)の母親役で知られるダイアナ・リン、昨年、TIFFで上映された『西湖畔に生きる』で、アジアフィルムアワード最優秀主演女優賞を受賞したジャン・チンチンの共演も見どころだが、なんといっても本作で心を鷲掴みにされるのは、中国のトップスター、イー・ヤンチェンシーの役に徹しきった感動的な演技だろう。
ワールド・プレミアとなる上映を終えたばかりの、監督、脚本家、プロデューサー、そして素敵な俳優の皆さんにお話を伺った。
──この物語の成り立ちを教えてください。
ヨウ・シャオイン(以下、ヨウ):私の母が所属するシニア合唱団に障害を抱えるひとりの男の子がおりまして、鼓手を務めるその子と周囲にいる人々に着想を得て、脚本を書きました。

ヤン・リーナー(以下、ヤン監督):これまで私が映画の中で描いてきたのは、がん患者であったり、アルツハイマーであったりと、病を患いながらも懸命に生きる人たちです。だからこれもその延長にある話として、興味を持ちました。

イン・ルー(以下、イン):実は私たち30年来の友人で、一緒に映画を作ってきた仲なんです。2020年にヨウさんからこの題材を聞いて、脳性麻痺の子がどう社会と関わりを持って生きるのかを伝えたくて、この企画を立てました。

ヤン監督:脳性麻痺の方は全世界で1700万人いて、そのうちの600万人は中国にいると言われています。その一人ひとりには誰もが持つ夢や欲望があるわけで、彼らもまた普通の人間として生きていることを、私はチュンフーの姿を通して訴えたかったんです。
──そのチュンフーを演じたイーさんに伺います。アイドルの貴方がこの難役に挑戦した理由を聞かせてください。
イー・ヤンチェンシー(以下、イー):確かに難しい役なんですが、僕は興味を掻き立てられました。実は、ここにいるイン・ルーさんと初めてご一緒した『送你一朵小紅花』(20/日本未公開)でも、僕はある病気を抱えていながら、ちゃんと普通に生きたいと望む人の役を演じています。アイドルは僕の仕事のひとつの柱ですが、もうひとつの柱である俳優の仕事の中で、僕は難しい役に挑戦してみたい気持ちがあるんです。

──私は以前、脳性麻痺の方の取材をしたことがありますが、そこで出会った人たちと映画の中のイー・ヤンチェンシーさんの違いが分からなかったんです。どうやって彼らの一挙手一投足を身につけたんでしょう?
イー:僕にとって演技に取り組むことは、何かを演じるというよりも、ある状態を見つけにいく感じです。今回、脳性麻痺を抱えるチュンフーを演じるのに、医学書とか資料を読んで脳性麻痺の方が筋肉をどう動かすのか勉強しましたが、緊張やこわばりの状態は人それぞれなのを知って、 自分の筋肉に見合ったチュンフーの動きを作っていきました。
イン:なにぶん難しい役柄ですから、最初は顔に特殊メイクをする話もしていたんです。けれどもそれではリアルな感じが出ないということで、彼自身、特殊メイクはやらないと決めて演じることになりました。
ヤン監督:特殊メイクに頼らず、ワンシーン、ワンシーン何度も繰り返しリハーサルをして、役を作り上げていったわけです。映画の中で、脳性麻痺の人が入っている施設にチュンフーが行く場面がありますが、あそこに登場する方々は本当の脳性麻痺の方々です。見事に溶け込んでいるのがおわかりいただけます。
──おばあさん役のダイアナさんは娘とうまくいかない気苦労を抱えながらも、明るいキャラクターで物語を引っ張っていく役です。役をどう理解して演じられましたか?
ダイアナ・リン:このおばあちゃんが娘とうまくやれないのは、性格の不一致もありますけど、このふたつの世代の間で中国社会が大きく変化し、両者の生きる道に隔たりが生じてしまったことも関係しています。自分ではなす術もない境遇に追い込まれて、娘に愛情深く接してやれなかった思いがあって、それを孫のチュンフーを世話することで補おうとするんです。

──ジャン・チンチンさんは愛されないまま育って、息子のことも愛せない母親を演じています。鬼気迫る演技を見せた『西湖畔に生きる』(23)と違い、感情をずっと溜め込む役柄です。
ジャン・チンチン:私が演じたこのお母さんは、息子のチュンフーを健康に生んであげられなかったつらさを抱え、母親として充分な愛を注げないでいます。 どういう目で息子を見つめればいいのかわからないから、いつも伏し目がちでいる難しい役です。私はいまだにこの母親をどう演じればよかったのかという答えを見つけられません。中国でよく映画のことを「悔いの残る芸術」と言いますが、私もまたこの役について、やり残したことがあると思っています。いつもそうだから映画に心魅かれてるんでしょうけど(笑)。

──ジョウ・ユートンさんは、チュンフーが恋心を抱く若い女性を演じています。ダイアナさんやジャン・チンチンさんの役どころと違って人物背景が劇中に描かれないので、役を掴むのは難しかったのでは?
ジョウ・ユートン:脚本家のヨウさんや監督のヤンさんとお話しして、ひと通り役について理解しましたけど、どんな過去を背負って生きてきたのかは自分なりに考えました。私の理解では、彼女は人類学を学んでいましたが挫折して、いま何をしていいのかわからない、そうしたぼんやりした状態にあります。それで外見は明るくて、生き生きしていても、内面に虚しさをいっぱい抱えているんです。

──チュンフーがスーツケースに入る場面は、象徴的にそれまで見せてきた事柄が一気につながる名場面です。あのアイデアは、脚本家のヨウさんが思いつかれたんでしょうか?
ヨウ:あそこで回想シーンを入れるということは私が脚本に書きましたが、どういうふうに表現するかは後で決めていきました。最初は箪笥の中に入る設定にしてあったけど、イー・ヤンチェンシーさんがスーツケースのほうがいいんじゃないかとおっしゃって、そっちのほうがいいなあと。確かに父親がよく出張に行く家庭では、スーツケースがごろんと床に置きっぱなしになっていたりしますからね。このシーンのあらましが決まったところで、どういう流れで回想に入るかというその前段の展開も、だんだん決まっていきました。
イン:あのシーンは本当に何度も別のバージョンを試しながら撮ったんです。スーツケースの中にいるのは脳性麻痺のチュンフーなのか、それとも健常者のチュンフーなのかというのもだいぶ議論した点で、映画の中で皆さんが目にできるチュンフーは後者です(笑)。
ヤン監督:このシーンでは猫も出てきますが、あれもイー・ヤンチェンシーさんのアイデアなんですよ。あの猫はちゃんと4本足のある健常者の猫です。だからこのシーンというのは、チュンフーの内なる願いがイマジネーションとなって膨らんでいるというイメージです。
──小林武史さんに音楽を依頼されたのはどなたのアイデアでしょうか?
イン:私です。今回、映画音楽についてはそれ専門の作曲家ではなくて別の人を探していて、『スワロウテイル』や『リリィ・シュシュのすべて』の音楽を書いた小林さんに作曲していただきました。小林さんとは国際合作ということになりましたけど、全然距離を感じさせない方で、今回本当に楽しく仕事ができてよかったです。
インタビュー/構成:赤塚成人(四月社)