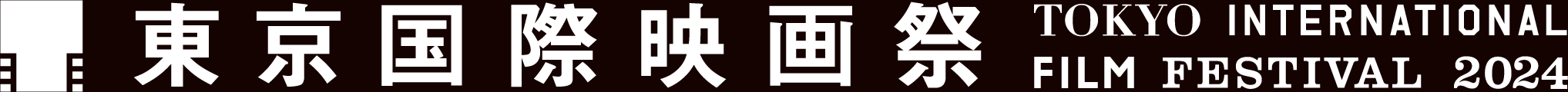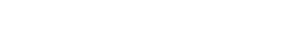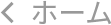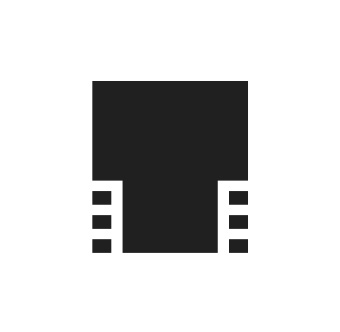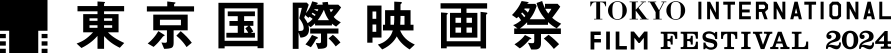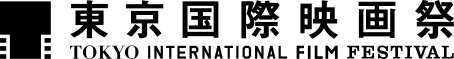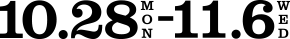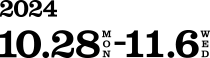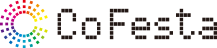東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月4日
コンペティション
『トラフィック』
テオドラ・アナ・ミハイ(監督・中央)、イオヌツ・ニクラエ(俳優・左)、ラレシュ・アンドリッチ(俳優・右)

若いルーマニア人夫婦のナタリアとジネルは、豊かな生活を求めて国を離れ、西欧へ移住。ところが、彼らの生活は次第に困窮していき、QOLはだだ下がり。そんなときに彼らは美術館強盗計画に加担することになり…。
2012年、オランダ・ロッテルダムにあるクンストハル美術館で起きた絵画窃盗事件をもとに、東西ヨーロッパの経済格差に切り込んだ社会派『トラフィック』。ルーマニアを代表する映画作家クリスティアン・ムンジウが、脚本と共同プロデュースを担当した本作で、監督を努めたテオドラ・アナ・ミハイ、そしてともに助演を努めたイオヌツ・ニクラエとラレシュ・アンドリッチに、事件のことや本作キャスティングなどを振り返ってもらった。
──まず監督に。
本映画祭のデイリーペーパーの取材で「クリスティアン・ムンジウ監督から断れないようなオファーを受けた」とおっしゃられています。その断ることができないオファーとはいったいなんだったのでしょう?
テオドラ・アナ・ミハイ監督(以下、ミハイ監督):クリスティアンさんとは10年ほど前に会ったのですが、「クリエイティブな意味でコラボレーションしましょう」と言われたんですね。恩人でもある彼にこういう頼まれ方をされたら、クリエイターとしてはお断りできません。
彼との出会いは、私の初監督作であるドキュメンタリー映画『Waiting for August』(14)。彼がそれを観て気に入り、自分の生まれ故郷に招待していただいたんです。その時、「あなたは今何やっているの」と聞かれたのですが、ちょうどそのとき私はメキシコで『母の聖戦』(2021TIFF審査員特別賞受賞)を撮っていたので、その話をしました。すると、「僕がプロデューサーになりますよ」と話が膨らみましてね。結果、共同プロデューサーになってくれたのです。
『母の聖戦』はテーマ的にも大変な作品だったのですが、コロナパンデミックの真最中だったので、撮影に際しての苦労がたくさんありました。なんとか完成した作品は、カンヌ映画祭の「ある視点」部門で勇気賞を受賞しまして、クリスティアンさんはとても誇りに思ったようなんです。「今度は一緒にクリエイティブな意味で協力しあってコラボしようよ」と言ってくれて…。それでこの作品の話になり、私が東欧、西欧の両方で育っていることもよくご存知だったので、私が監督するのにはピッタリじゃないかとおっしゃってくださったんです。

──たしかにそれは逃げられないですね。
ミハイ監督:ほんとそうですよね(笑)。
──デイリーペーパーでは、監督とムンジウ監督との間で議論になったことがあるとありました。こんなにはっきりと「ぶつかった」ということを、ここで言う監督はいらっしゃらない。しかも、おふたりの仲がよろしいことをうかがったらなおのこと。何でぶつかったのかうかがいたいのですが、よろしいでしょうか?
ミハイ監督:クリエイティブなプロセスで、色んな議論はしてきました。が、編集の段階で私は作家主義的な方向に向きたがり、クリスティアンさんは観客が喜ぶ映画を好んでいたことでちょっとぶつかりました。
彼はプロデューサーとしてあるステージにきているということもあるし、地元の観客のことを考えると、作家主義的なアートハウス映画では少々難しいと思ったようです。ルーマニアの傾向として、映画祭的なアート映画に大衆は背を向けるんですよ。それは、アート映画=エリート主義に見られているから。そのため、ふたりの間で会話がピンポンのように行なわれました。いい形、いいバランスを探すための衝突だったので、関係性が悪くなることはありませんでしたよ。
──謎がとけました。失礼なことを聞いてすみません。
ミハイ監督:すごくいい質問だと思います。クリスティアンさんには非常に明確なアイデアがあるし、監督というクリエイターは必ずしも簡単な人たちではなく、自分のやりたい方向というのがあることを理解しています。でも、そのクリエイティブなプロセスにおいて火花が散ることは、私はいいことだと思うんですね。プロジェクトがよくなると思っています。
──ごもっともです。そして文字通り、彼が求めていたクリエイティブな意味でのコラボレーションというのがそこで生まれたっていうことですもんね。
ミハイ監督:そうですね。本作はニュアンスが大事なので、クリスティアンさんと私は脚本段階からすごく近しく仕事をしていました。それに私はこの映画のことを、よく理解できる、というふうに思うんです。というのは、私の経験は彼とは違うから。
私はベルギー育ちの移民の子どもです。私の両親は、共産圏時代のルーマニアからベルギーに政治亡命しました。なので、ベルギーをはじめとする西欧、そして東欧、両方の文化がよくわかりますし、双方にある強みと弱みもよくわかります。また“恥の感覚”というのもよくわかるんですよね。その理解があるからこそ、さまざまなレベルで詳しく議論を重ねていきました。
また、本作は私にとって初めてのルーマニアで撮影する映画。そのため、クリスティアンさんとはキャスティングでも深く相談しました。アナマリア(・ヴァルトロメイ)さんを主演に選んだのは、彼女の演技が素晴らしいということはもちろんですが、彼女が私と同じく、生まれはルーマニアでフランス育ちという西欧と東欧のバックボーンを持つ非常に似た人だったからです。彼女にとっても本作は初めてのルーマニア人の役でした。
──本作で描かれている事件は、2012年に実際にクンストハル美術館で起きた大事件として世界的に報道されています。みなさん、この事件に対する印象はどんなものだったのでしょう?
ミハイ監督:10年以上前の事件なので、何となく聞いたことあるなという感じでした。事件はほんとに悲劇的ですし、映画化するにはいろんな可能性があるとも思っています。非常に実存的なテーマだけに、すごくタイムリーですよね。じつはこの脚本は色んなバージョンがあり、私は事件にフォーカスしていた最初の脚本より、もっとキャラクターに寄り添った親密さを出したいと思いました。特にジネル(イオヌツ・ニクラエ)とナタリア(アナマリア)のカップルに近づきたいというふうに思ったんです。
それで、脚本についてのブレスト中、「これは犯罪映画だけど、実際の犯罪なしで書いたらどうか」という提案をクリスティアンにしました。でも最終的には、「あなたの脚本なんだから、あなたの好きにすればいい」と言っちゃいましたけどね(笑)。
ラレシュ・アンドリッチ(以下、アンドリッチ):この事件を知ったのがいつかはっきり覚えていないですが、ネットの記事で読んだのが最初でした。それを読んだ時は、自分の国の人が起こした国際犯罪ということで、すごく恥ずかしかったです。
でも、これが映画になる、しかも僕が参加する、となった時はすごくわくわくしましたね。完成した今も事件についてはちょっと恥ずかしいところはあるけれども、自分の役がすごく気に入っているのです。悪い役だけどすごくいいなと思っていて。

ミハイ監督:あなた、いつも被害者役ばかりやるから。今回は逆の立場の役だから嬉しいのよね(笑)。
アンドリッチ:そうそう(笑)。
イオヌツ・ニクラエ(以下、ニクラエ):私もニュースを読んだことで事件を知りました。でも、ルーマニアではそんなに大騒ぎにならなかったんですよ。むしろ、盗みだすのに2分半しかかからなかったっていうおもしろエピソードみたいな感じで。
でも、オランダでは大事件だということを知って、ルーマニア人としてのアイデンティティクライシスみたいな感じになりました。ルーマニア人にとっては可笑しい事件だけど、オランダ人にとっては悲劇的でトラウマになるような事件。感覚の違いがこんなにもあるのかと思いましたね。キャスティングの段階では、部分的な脚本だけ渡されたのですが、何か月か後に完成した脚本をいただき、すごくいいと思いました。あ、でも、ラレシュは全部見なかったんだよね?

アンドリッチ:そうそう。自分のパートだけ。
ニクラエ:僕と彼は出演時間の尺が違うから、彼は脚本を全部もらえてなかったのかもしれません。
──キャスティングのプロセスは? オーディションだったんでしょうか?
ニクラエ:じつは10か月かかっているんです。
──えええ!?
ニクラエ:長いですよね。待たされている間、しょっちゅうキャスティングディレクターに電話して、「どうなってるの?」と聞いてました。この仕事ができるのかどうかすごく心配でしたし、ほかのルーマニア人の俳優だったら誰がジネル役をやるかな、とか疑心暗鬼になっていました。最終的には無事キャスティングされて、すごくよかったです。
ミハイ監督:それには理由があるんです。ルーマニアで映画を撮るのが初めてだったので、ルーマニア人の俳優さんをよく理解するために、リサーチをしっかりしたかったんです。また、オーディションでは役者さん同士のケミストリーも見たかった。そのために、待機する時間が非常に長くなってしまい、彼らにとっては辛いことをしてしまいました。
でも、これは必要な時間だったと思っています。とにかく私たちはハイレベルの俳優さんが欲しかった。撮りたい内容に対して予算はすごく少なかったので、エラーを起こしている時間がなかったんです。しっかり役者さんを選んで、撮り始めたらサクサク撮れる人がよかったので、撮影前の準備にすごく時間をかけたんです。
アンドリッチ:僕は6〜7か月の待機で、イオヌツよりは短かったですね(笑)。オーディション用に自分で撮った映像を提出し、その後すごく待たされて。その後連絡があって、イオヌツと一緒にシーンをやって、自分としてはうまくいったと思ったのですが、また長く待たされました。きっと私は落ちて、ほかの人を選んだのかなと思ったほど。
ただ、オーディションに呼ばれるたびに、「もうちょっとやって」と言われたので、気に入ってくれているのかも、という期待はありました。
──予算の都合で撮影時間は短かったとのこと。失敗できない撮影だけに、リハーサルやワークショップもしましたよね?
ミハイ監督:バジェットに対しては、非常に野心的な映画のプロジェクトでしたから、リハーサルはもちろんやりました。それに、リハーサル中も撮影していました。リハでたまに宝石のような素晴らしい瞬間が生まれたりすることもありますから。
アンドリッチ:リハーサルはセリフ中心でしたね。リハの時間をあまり多く割けなかったので、物理的な尺…ここからここまで行くのにどれくらいの時間がかかる、とかいったことについては練習できなかったんです。なので、そこは私たちが撮影現場で臨機応変に合わせていきました。
イオヌツ:僕はかねてからそんなにリハーサルを必要としないと思っています。現場主義で、監督や共演者とその場その場でコネクトしてやっていくことが必要だと思うから。たしかに普段しないことは練習しましたよ。たとえば、ボートを運転したり、左ハンドルの自動車とか。そのために講習受けて学ぶことはたくさんありました。
ミハイ監督:リハーサルしすぎるとシーンが生きないものね。
イオヌツ:そうそう。リハーサルで良いのができちゃうと、ちょっと機械的になってしまうじゃないですか。そのときどきの新鮮さを残しておかないと。演技はその場・その瞬間でのことなので、芝居であってもその場で起こっていることに合わせていくが大事だと思います。
──現場には共演者の芝居や衣装、セットなどいろいろな要素がありますが、芝居は何に影響されることが多いでしょう?
アンドリッチ:僕にとっては全部が助けになります。コスチュームやセットからも新しい視点を貰えますから。違うコスチュームを着けると自分の態度も変わるし、その役を感じることができるんですね。セットも違う世界に入りこむためにはとても助けになります。
ニクラエ:舞台劇と映画の比較をしますね。舞台って演出家が俳優に向かって、「そこに山があるから山を見た気持ちになって呼吸してみて」みたいなことをやらないといけないけれど、映画の場合は、実際に4時間かけて山に行って、本当の山を見て息をすればOK。
そのために、ライティングの人たちなどをはじめとする現場クルーの協力がすごく大事です。彼らが私たちに優しく協力してくれたら上手くいくし、あまり気にしないでガンガン音立てたりされると、芝居の質も下がってしまうわけです。
ミハイ監督:何度も経験し、実感していることですが、全部の部門の人が一丸となることが重要です。メイクも大事だし、コスチュームも大事だし…。それぞれのスタッフ、キャストに与えられた仕事がすべてうまくいくと、マジックが起こる。低バジェットで制約がたくさんあったけど、そのマジックが起きたことで本作はうまくいったのだと思います。

インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)