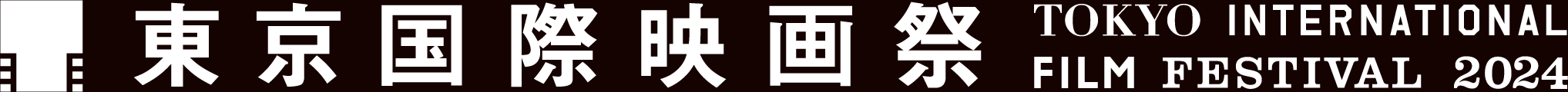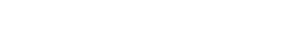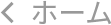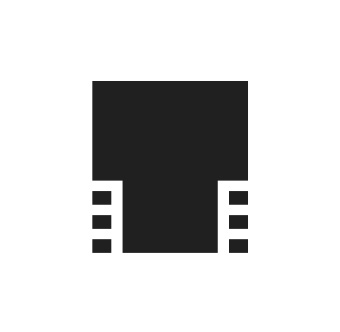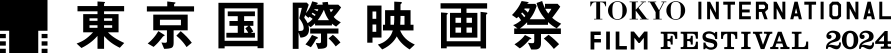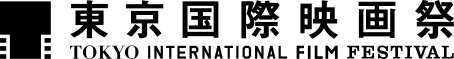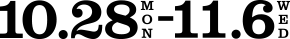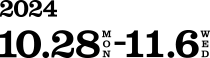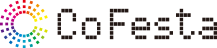東京国際映画祭公式インタビュー 2024年11月4日
コンペティション
『死体を埋めろ』
マルコ・ドゥトラ(監督)

ブラジルの片田舎で、道路ではねられた死体を回収する仕事に従事する男エジカルは暴力的な悪夢に悩まされる日々を送っている。さらに恋人のネッチがカルト宗教に入信したことで彼の日常は大きく変わっていく――。ブラジル。サンパウロ出身のマルコ・ドゥトラの6作目は悪夢のような世界が描かれる。2017年の『狼チャイルド』がロカルノ国際映画祭で激賞された監督のホラー、ファンタジー嗜好が伺える、シュールな仕上がりだ。
──小説の映画化ということですが、どんなかたちで映画化を進めたのですか?
マルコ・ドゥトラ監督(以下、ドゥトラ監督):この小説は2019年に出版されました。アナ・パウラ・マイアの7冊目か8冊目の本だったと思います。私は彼女の作品を気に入っていましたが、この本は出版されたばかりでまだ読んでいませんでした。プロデューサーに勧められて読んだのです。彼女の作品には同じ主人公が登場し、さまざまな人生の段階が描かれるのですが、この作品は、終わりが来る黙示録的な展開と言いますか、聖書的なアプローチが面白いと思い、脚本を書き始めました。
2020年から2021年の間、私はコロナに罹り、今までにない経験をしました。人がまったく想像できなかった経験をしながら世界の変化を体験したことで、別の層が加わったという感じがしました。地球温暖化や紛争、政治的な混乱をこの物語の中に入れようと思いました。

──コロナに罹っているときにどんな考えを抱かれたのですか?
ドゥトラ:私自身は重症にはなりませんでしたが、いとこがふたり亡くなり、友達もふたり亡くなりました。世界がどうであれ、ブラジルにはコロナは存在しないというのが政府の認識でした。にもかかわらず、北部では死体が山のように積みあがり、集団埋葬のようなかたちで人が埋められている。本当に混沌とした状態でした。そんななかで私がこのスト-リーを書くというのは、とてもアイロニックなことでもありました。
──悲惨な状況でしたね。
ドゥトラ:世界の終りのことを書く気はなかったのですが、こういうことが起きて、非常に喪失感がありました。同時に物凄い混乱もありました。国は公にはコロナを認めていないが、周りでは人がたくさん死んでいる、一体これはどうなっているのだという思いを映画の中に込めました。
この時期、皆が世界は終わると言い始めました。世界が終わるとしたらどうやって終わるのか? 病気が蔓延して終わるのか、それともエイリアンに人類がやられてしまうのか、どこかで戦争が起きて世界が終わってしまうのか。そして私は、これを書くべきなのかと何度も悩みました。
最終的に書くことにしたら、こうして日本にも来られましたし、何百人もの観客と一緒に映画を見ることもできて、今は癒しのプロセスに入っている気がします。
──主人公が死体片付け人ということはとても象徴的な意味を持ってくるわけですね。
ドゥトラ:原作者にふたつのバージョンの脚本を読んでもらい、自由に映画化していいと言ってもらいました。原作者は死体片付け人にリサーチをかけて物語にしています。ファンタジーのように思われるかもしれませんが、実際にそういう仕事があるのです。ただ実際のところから物語を膨らませてはいます。
──最も心掛けたこと、注意して描いたことは何ですか?
ドゥトラ:ものを書く時には、必ずチャレンジするよう試みています。伝統的ルールや構造とは違うものにチャレンジしたいと思っています。その方が面白いし、それは自分の遊び心ですね。
本作で試みたのは、ふたつの要素をひとつの映画に合わせて落とし込むということです。ひとつは、大きな世界で起こっていること。世界が終わってしまうというような概念ですね。世界はいつ終わるのかということについては、何十年後ではないけれど、わりとすぐに終わってしまうのではないかと私は思っています。今回の作品では、私の中では、世界はエイリアンに侵入されて終わるという設定にしています。ただそれは、観客に見せる必要はないと思って書きました。
もうひとつは、正反対の主観的なものです。主人公は過去を隠して、ほとんど話をしません。生活や仕事の中に死とか暴力というものが関わっていたというふうに設定しました。

──ユニークな発想ですね。
ドゥトラ:7歳ぐらいからホラー映画、大人の映画も見ていました。アルフレッド・ヒッチコック監督の『鳥』を観た時は、突然鳥が攻撃を仕掛けてくることに対する説明はないけれど、暴力やロマンス、ユーモア、色々なことがひとつの映画で表現できることに感動したのを覚えています。溝口健二監督の『雨月物語』もそうですね。映画はストーリーを語るということ以外に、こんなにたくさんのことができるというインスピレーションを受けました。
──灼熱の高速道路上で、いかにも匂ってきそうな死体を処理する人間が描かれ、悪夢のようなイメージがありましたね。
ドゥトラ:匂いのことを言っていただいて嬉しいです。五感を使って世界を伝えたいと思っていました。観ている方がそれぞれ自由に観て、何かを感じ取っていただければ幸いです。

──新作のご予定はありますか?
ドゥトラ:『狼チャイルド』で仕事をしたフリアナ・ロハスと一緒に『ハングリー』という作品を準備しています。ジャンルはホラーですね。大学で何かに感染してしまって、生徒と先生の間で断絶が生まれるという物語を書いているところです。
インタビュー/構成:稲田隆紀(日本映画ペンクラブ)