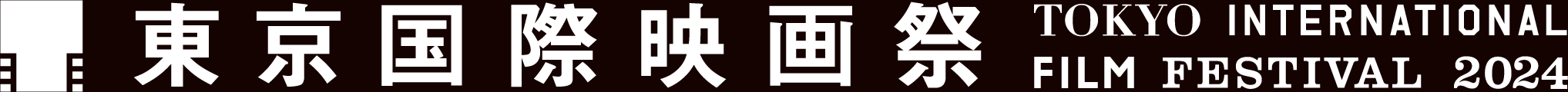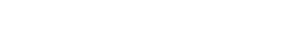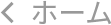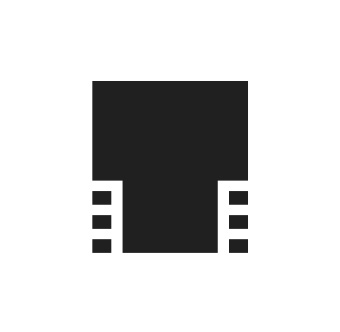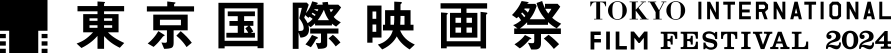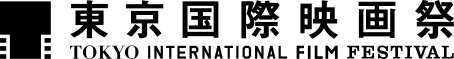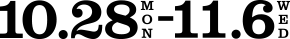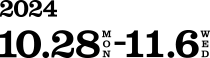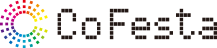10/31(金)「PFFアワード2024」グランプリ受賞作品『I AM NOT INVISIBLE』上映後に、川島佑喜監督(中央・『I AM NOT INVISIBLE』)、畔柳太陽監督(左・『松坂さん』)、カコ・アニカ・エサシ監督(右・『END of DINOSAURS』)をお迎えし、Q&Aが行われました。
司会:PFFディレクター荒木啓子さん(以下、荒木D):今回は、「PFFアワード2024」グランプリ受賞作品『I AM NOT INVISIBLE』、審査員特別賞の『松坂さん』と『END of DINOSAURS』の上映3本立てでしたので、皆さん、頭の中でいろいろと整理をされているかと思います。
3作品上映になった経緯は、私たちの映画祭(ぴあフィルムフェスティバル)は9月に開催されるため、賞の決定を待っていると東京国際映画祭のプログラムに間に合わないということで枠を置いていただいているのですが、今年のグランプリが長編ではなかったため、枠の時間いっぱいを使わせていただき、お客様に新しい作品を観ていただこうということで、3本立てになりました。監督の皆様、一言ずつお願いいたします。
畔柳太陽監督(以下、畔柳監督):今日は観に来てくださり、ありがとうございました。
カコ・アニカ・エサシ監督(以下、エサシ監督):『END of DINOSAURS』監督のカコ・アニカ・エサシと申します。今日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
川島佑喜監督(以下、川島監督):『I AM NOT INVISIBLE 』(PFFグランプリ)の監督をした川島佑喜です。今日はハロウィンなのでタクシードライバーの服で来ました。
エサシ監督:「ハロウィーンの仮装をしていきましょう」と言ったら、畔柳さんに「嫌ですよ、そんなの」と言われて。だから私たちは着てこなかったんですけど(笑)
にもかかわらず、(川島さんは)仮装をしてきてくれたんですよ(笑)
荒木D:裏切り者ですね、2人は。
エサシ監督:そうなっちゃいました、結局。
荒木D:早速友情にヒビが入ってますが(笑)今日はハロウィンですね。でも、じゃあ(川島監督は)モヒカンに刈って来るともっと良かったよね(笑)。というわけで、3人はとても仲が良さそうなのですね。改めて、3人とも1ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりに再度作品をご覧になって、新たな発見があったかと思います。この組み合わせも初めてです。それぞれ質問し合っていただけますか。
川島監督:(畔柳監督への質問)『松坂さん』についてですが、昨日お話した時にセリフで表現することの重要性についてお話をされていましたがそれについてお伺いしたいです。今回の『松坂さん』において、映像や演出で表現した部分と、あえてセリフで説明した部分の違いや意図だったりはありますか。
畔柳監督:セリフが重要というのは、頑張って映像で見せようとして伝わらないより、つたなくても言葉にすることで伝わるんじゃないかという感じです。コンビニのシーンで、印刷したてのコピー用紙が温かいという描写を入れたいと思っていました。「温かい」と後からナレーションでつけていますが、それは(セリフで)言わないと伝わらないなと思って。今ぱっと思いついたのはそのコンビニのシーンです。
川島監督:直前まで迷った感じですか。
畔柳監督:そうですね。「温かい」と言えば伝わるなと思って。最終的にはそうしました。
川島監督:セリフがなくても、ドアが開いた瞬間の空気の冷たさみたいなのは、「寒い」と言っていなくても分かる。こうやった(コピー用紙に触れた)時に温かいのだろうなと思いましたが、セリフが蛇足になっている感じはなくて。セリフがあることで、みんなが経験したことのある、プリントした紙の温かさを想起できたと思います。机で寝てしまって、朝起きると書いたペンの跡が(手や腕に)残っているとか。あれも多分、セリフじゃなく画的な表現で留めた部分だと思っていて。何回か観た上でですが、描くところ、言うところ、言わないところの感覚的なバランス、こだわりを感じました。
畔柳監督:ありがとうございます。
エサシ監督:「1人っ子みたいな自転車のこぎ方」とは、どんなこぎ方なのでしょうか。普段から思っているのですか。
畔柳監督:最初、素直に、「1人っ子の自転車のこぎ方だと思った」というナレーションにしていましたが、 絶対に分からないと言われて。「誰にも共感されないかもしれないけど」というナレーションを加えれば、少しは伝わるんじゃないかという意見をもらって。そうしました。
どこを見ているかというのは、比較といいますか。例えば、友達に兄弟がいる子の自転車のこぎ方を見たことがあって、 その記憶との比較で違うということは1人っ子かと思うという。飛躍して人を捉えているということかなと。
エサシ監督:大事ですよね。結局1人っ子じゃなかった、みたいな。現実は分かりませんが。我々が見ている、思っている人たちとの違いを感じました。
畔柳監督:本当にそう。人を飛躍して捉える癖があって。この人はこういう人なんじゃないか、こういう人に決まっている、みたいなことをいつも思ってしまって…その想像が違ったってことが生きていて多かったので、このような表現をやりたいなと思いました。
川島監督:劇中の「寂しい人だと思ったと言われたのがすごく嫌だった」という部分にびっくりして。いや、そうだよなと思ったんです。「寂しい人だと思った」という印象で、足りない2人がお互いに引き寄せ合って恋をする、みたいな方が物語として綺麗ですが、人って知らないところや分からないところばかりだから。そういうリアリズムみたいな部分、すごく好きだなと思いました。
エサシ監督:ホールで話している時に裏から入る引きの画が1つあるのと、2人が歩いている時に正面から引いてフォローするのではなく、斜め打ちで出ますが、急に客観的視点のカット割りに入っているのですか?
畔柳監督:カット割りですよね。
エサシ監督:事前に決めているのか、現場で感覚で決めているのか、自分の中で変わるのか。
畔柳監督:自分の中で変わります。基本的に、カット割りは現場でみんなで決めますが、 編集でどうにかしようとすることも多いです。
エサシ監督:結構撮っている感じですか?
畔柳監督:そうですね。撮っていて、編集でなんとかなる、なんとかしようとしちゃうという。それで、主観と客観が入り交じるような印象を与えるのかなと思いました。
川島監督:(エサシ監督に)流れで『END of DINOSAURS』の話をしても良いですか。『END of DINOSAURS』は エサシ監督自身が主演なので、撮る時にカメラ側にいられないわけですが、カメラへの指示や演出はどれぐらい自分で決めて、どれぐらい任せていますか。
エサシ監督:ほとんど任せています。 事前に、こういうところはこういうイメージで撮りたい、みたいな話ができたりできなかったりするので、そこを話した上でチームに任せています。
川島監督:撮影技術部とは今までにも映像を撮ったことがあるような、信頼感があるチームなのですか。
エサシ監督:そうですね。今回の録音とカメラは、脚本を書いてくれた片山 享さん(以下、片山さん)です。片山さんも監督さんと役者さんもやられてるので、片山さんの現場では私がスタッフとして入っていて。
今回の現場は私が監督でしたので、もちろん役目や立場は違いますが、考え方や感覚、ボキャブラリーが共通している部分があるので、信頼感はすごくあります。
川島監督:いいですね。
エサシ監督:ありがとうございます。幸せですよ。
川島監督:畔柳さんもそうですが、劇映画の現場への憧れや羨ましさはずっとあるので。
エサシ監督:作りたいですか?劇映画とドキュメンタリー。
川島監督:向いていなくて。大学で、短編なども何本か作りましたが。やはり、コミュニティが向いていなくて、コミュニケーションが苦手なので。
エサシ監督:ドキュメンタリーは比べるものではありませんが…ドキュメンタリーと劇映画がどう違うんだ、みたいな部分もありますが、どのように現地でコミュニケーションを取ったのですか。
川島監督:フィリピンなのでタガログ語という言語が主で、 都会の人やお店の人はタガログ語と英語の両方喋れる人も多くて。私の祖母もそうですが、学校に行っていない方、貧困層の方はタガログ語しか喋れない場合が多いです。祖母の家に2週間ほど滞在しましたが、衝動的に行きたい、おばあちゃんに会いたい、という感じで行きました。
スラムで撮影することは全く考えていませんでしたが、祖母の知り合いの知り合いにスラム出身の方がいて。その方は英語も喋れるので、私は英語で質問して、その人がタガログ語で代わりに質問してくれて、それを英語に直してくれて、みたいな。自分はもう英語だけで。特異なことは、ぼんやりとした英語訳でしか返答を理解できないので、その場ではなんとなくで撮っていて。持って帰ってきてから正確に音声で翻訳をすると、こんなことを言っていたんだなとか。
感動したのは、最後の方のおばあさんで、「私(川島監督)ぐらい若かった頃に経験した美しい思い出がたくさんあるからここを離れたくない」みたいなことは、その場では掴めていなかったニュアンスでしたので、こんなにいいこと言ってくれていたのだなと思って。
唯一、スラムで英語で喋ってくれた同い年ぐらいの子は、あの場で唯一、大学院に行った子で。あの子だけが進んでいた。スラムに対して悲観的で、見栄えがいいものではないと言っていて。外の世界を見たことがあるからだろうなと思いました。
ベラベラ喋ってしまいましたが、フィリピンの国民性もありますが、幸せだという人がすごく多いんです。それは、その環境にいるしかないから言い聞かせてる部分があったり、他と比べられないからだったり、色々な要因があると思います。
幸せだって言っているから、これでいいって言っているからいいじゃん、みたいな。本人がいいって言っているのだからとも思えないけれど、本人がいい、幸せだって言っているのが全部嘘で、本当はすごくかわいそうな人たちだという風にも言いたくないみたいな。そのモヤモヤした気持ちが撮影中も編集中もずっとありました。撮影中も編集中も、何も用意せず、その場その場で考えていた。計画せずに、なるようになれという感じでなったのでよかったです。
だけど、これからはならないかもしれない。劇映画とドキュメンタリーを審査の場で一緒に並べていただいて。ジャンル分けはありませんでしたが、作り方の感覚が結構違うのかなと。
観るのは映画が好きですが、劇映画を作るのは難しいと思いました。観ることが本当に好きなので。
荒木D:川島さん、今お話されましたが、インタビューの質問は考えていたのですか。最初から自分で。
川島監督:(フィリピンに)着いてからスラムを撮りたいとお願いしました。ダメと言われてごねていたら、連れていってもらえることになりました。英語を話せる人がいるかわからなかったので、小さいメモに大きい文字で書いて、シンプルで分かりやすい、短い質問を何個か用意しました。
荒木D:この質問を聞こうと決めたのは取材に行った時ですか、最初からですか。
川島監督:1人目にインタビューした時に聞いた内容を皆にも同じように聞きました。そうすることで、回答に違いが出て綺麗にまとめられるかもしれないなと。フィールドワーク的な取材は時間がかかるので出来ませんでしたし、うまく質問を深掘りして調査できる気もしなかったので、あえて分かりやすいフレーズで、その人の人生を想像させることができたらいいなと思いながら質問を考えました。
荒木D:ありがとうございます。短い時間でしたが、3人とも次作を準備中ですので、ぜひ次の作品も観ていただきたいと思います。
今、映画を撮りたいと思っている人たちは、作品を人に観てもらうことによって劇的に変わっていきます。彼らがこれからどうなっていくのか、ぜひ観続けていただけたらと思います。